このたびの記録的な豪雨により、西日本を中心に大きな被害が生じました。
本学会の会員の皆様を含め、この平成30年7月豪雨で被災された方々に謹んで心より
お見舞い申し上げます。
関西英語教育学会(KELES)
会長 里井 久輝
このたびの記録的な豪雨により、西日本を中心に大きな被害が生じました。
本学会の会員の皆様を含め、この平成30年7月豪雨で被災された方々に謹んで心より
お見舞い申し上げます。
関西英語教育学会(KELES)
会長 里井 久輝
去る6月18日の早朝に、大阪府北部を震源とした大きな地震が発生しました。
本学会の会員の皆様を含め、この地震で被災された方々には謹んで心よりお見舞い申し上げます。
関西英語教育学会(KELES)
会長 里井 久輝
2018年度関西英語教育学会(KELES)第23回研究大会を下記の要領で開催致します。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
→ プログラムのダウンロード
→ アブストラクトのダウンロード
2018(平成 30) 年
6 月 9日(土)9:20~17:30(9:00受付開始)
関西国際大学・尼崎キャンパス
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番23号 → アクセス
関西英語教育学会会員・LET関西会員:無料
非会員(一般):2,000 円
非会員(学部学生・大学院生):1,000 円
*学生証をご提示下さい。提示がない場合は一般参加費となります。
*事前申込の必要はございません。当日会場にお越し下さい。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
①9:30~9:55 ②10:00~10:25 ③10:30~10:55
① 事例報告:初年次英語科目のクラスター化の効果:習熟度と動機づけに関する量的分析/井上 聡 (環太平洋大学)
② 研究発表:自発的に英語でコミュニケーションを図ろうとする意思の形成について—音楽とプレゼンテーションを用いた量的研究—/北岡 一弘(近畿大学)
③ 事例報告:英英辞典指導法: 『コウビルド英英辞典(改訂第8版)』の場合/秦 正哲(兵庫医療大学)
① 事例報告:しそ栽培を通して考える力を育成する英語教育の実践 —「ハンズオン授業」をテーマにした実践例—/堀内 夕子(大阪キリスト教短期大学)
② 事例報告:Youtubeを活用した授業外学習?自律的学習を促すビデオリポート/ラムスデン 多夏子(京都外国語大学)
③ 事例報告:ディベートの導入は英語授業を活性化するかについてディベートしましょう/加藤 雅之(神戸大学)
「英語による『やり取り』に焦点をあてた言語活動をつくる5つのtips-小・中・高・大のつながりを見据えて-」
坂本南美(岡山理科大学)
○ 昼食は,大学周辺の飲食店をご利用ください。
○12:30~13:15 の間,総会を開催します。
④13:30~13:55 ⑤14:00~14:25 ⑥14:30~14:55
④ 事例報告:(普通の小学校での実践から)移行措置1年目の現在の状況からこれからの問題点を探る-新学習指導要領の実施に向けての方策を考える- /高木 浩志(宝塚市立逆瀬台小学校)
⑤ 事例報告:小学校国語・英語をつなぐローマ字指導実践/高松 理英子(元 兵庫県高砂市立伊保小学校)
⑥ 研究発表:英語教育についての言説と素朴信念 −ポッドキャスト番組の談話からー/泉谷 律子(大阪大学大学院生)
④ 研究発表:日本人中学生のスピーキング力育成に対するTPRとラウンド制指導法の有効性に関する実証研究—中学1年生段階での活用—/黒川 愛子(帝塚山大学)
⑤ 研究発表:日本語母語話者の英語発音の特徴:音声認識アプリを用いた分析/中西 のりこ(神戸学院大学)
⑥ 研究発表:外国語ライティング授業に関する一考察 —ライティング・プロセスと使用言語の観点から—/辻 香代(京都大学大学院生)
「この 英語騒動から見えてくること」
講師:阿部 公彦(東京大学)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2018年度(第23回) 研究大会 プログラム(PDF)
 【プロフィール】
【プロフィール】坂本 南美(さかもと なみ):岡山理科大学教育学部中等教育学科英語教育コース・准教授;公立中学校教諭として勤務しながら,研修制度にて2008 年に兵庫教育大学大学院学校教育研究科を修了。姫路市立の中学校,兵庫県立大学附属中学校を経て、2017年4月より現任校に勤務。ナラティブによるALT 研究,教師の成長,ペアワークなどの協働学習の研究を行っている。「英語科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」,「外国語活動の指導」「ICT活用教育」などの授業を担当。
新学習指導要領の英語では,5つの領域(聞くこと,読むこと,話すこと(発表),話すこと(やり取り),書くこと)の言語活動を通して,コミュニケーションを図る資質・能力の育成が求められています。現行の4技能の中の「話すこと」を「発表」と「やり取り」に分けて捉えることで,教師にも学習者にも話す活動の目的がより明確になりました。
本ワークショップでは,学習者が英語で「やり取り」をするための5つのtipsをもとに,中学校の英語授業で取り入れやすい言語活動を紹介します。活動を通して,小学校・高等学校・大学でもアレンジできる言語活動を体験しながら,英語の授業でmeaningfulな「やり取り」を生み出す活動をデザインしていきましょう。実践やディスカッションを通して、参加者の皆さんと意見を交換しながら方向性を探り,日々の授業への橋渡しとなる時間をつくっていきます。
 【プロフィール】
【プロフィール】阿部公彦(あべまさひこ):1966年生まれ。現在、東京大学文学部教授。英米文学研究。文芸評論。著書は『英詩のわかり方』(研究社),『小説的思考のススメ』(東京大学出版会),『幼さという戦略』(朝日選書),『名作をいじる』(立東舎),『史上最悪の英語政策』(ひつじ書房)など啓蒙書と,専門書としては『文学を〈凝視する〉』(岩波書店 サントリー学芸賞受賞),『善意と悪意の英文学史』(東京大学出版会)など。マラマッド『魔法の樽 他十二編』(岩波文庫)などの翻訳もある。
ホームページ: http://abemasahiko.my.coocan.jp/
「英語ができる」とはどういうことなのだろう。日本では一般に,「英語ができる」というと「英語がしゃべれる」と同義にとらえられることも多い。なぜこのような同一化がされるのだろう。また,それなら「英語がしゃべれる」とはどういうことなのだろう。
長らく日本人は「英語ができない」コンプレックスに苛まれてきた。もし「できない」のがほんとうだとすると,その原因はひょっとすると「英語ができる」=「英語がしゃべれる」と考えるようなメンタリティにあるのではないかというのが筆者の考えである。その理由を説明したい。
異なった考えをお持ちの方もおられると思うので,是非,建設的な意見交換をし,どうすれば日本の英語教育がこれ以上悪くならないかを検討したい。
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2018年度(第23回)研究大会 研究発表・公募フォーラム・アブストラクト(PDF)
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
全国英語教育学会第44回京都研究大会が,以下の通り開催されます。今年度は,関西英語教育学会(KELES)が担当の大会となっております。
全国の会員ではない,という方もいらっしゃいますが,折角の関西開催です。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。詳細は大会ウェブサイトをご覧下さい。
日時: 2018年8月25日(土)・26日(日)
会場: 龍谷大学・大宮キャンパス
〒600-8268 京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1
大会ウェブサイト:http://www.keles.jp/jasele2018/
2018年度関西英語教育学会(第23回)研究大会を下記の要領で開催致します。
本年度の研究大会は,6月9日(土)に関西国際大学尼崎キャンパスにて開催することとなりました。
今回も,研究発表・事例報告に加えて,公募ワークショップ・公募フォーラムの発表募集を行います。奮ってご応募下さい。多くの皆様のご発表・ご参加をお待ちしております。
2018(平成 30) 年 6 月 9日(土)
関西国際大学尼崎キャンパス アクセス
関西英語教育学会会員:無 料
非会員(一般):2,000 円
非会員(学部学生・大学院生):1,000 円 (※学生証を提示して下さい)
- 開会行事
- 公募ワークショップ/公募フォーラム
- 総会
- 研究発表・事例報告(口頭発表・ポスター・デモ発表)
- 講演 「この英語騒動から見えてくること」講師:阿部 公彦(東京大学)
発表者は、関西英語教育学会の会員にかぎります
※ 2018 年 5 月 7 日(月)までに,会員の方は 2018 年度の学会費を納入していることが必要です。非会員の方は、会員手続き(入会申込および会費納入)を済ませて下さい。入会手続きおよび会費納入が確認されない場合は、発表自体が取り消しとなりますのでご注意下さい。
※ 共同研究者は学会員であることが望ましいですが、必ずしも会員である必要はありません。ただし、当日の発表は学会員が行って下さい。
広く英語教育にかかわる理論的・実証的研究および授業実践に関する報告で、未発表のものに限ります。
日本語または英語
(1)研究発表 (理論的、実証的研究の発表)
(2)事例報告 (授業実践に関する報告)
(3)ポスター・デモ発表(ポスター発表・対面発表・教材教具などのデモなど)
(4)公募ワークショップ(1人または複数の講師による英語授業実践をテーマとした企画)
(5)公募フォーラム(コーディネータおよび数名の英語教育にかかわる理論的・実証的研究をテーマとした企画)
(1)口頭発表(1 件につき発表 20 分、質疑応答 5 分〜10分* プログラム構成によって質疑の時間の若干の変動あり)
(2)ポスター・デモ発表(発表コアタイム 60 分)
(3)公募ワークショップ・公募フォーラムは1件あたり90分です。
本ページの申込フォームから、必要情報(以下の内容)を入力して送信して下さい。
2018年4 月2 日(金) ~ 5 月 7 日(月) 23:59 まで
※期限厳守。期限を過ぎたものはいかなる理由があっても受け付けることができませんので,留意して下さい。
2018年5月9日(水) までに登録されているメールアドレス宛てに、電子メールにて通知します。
※5月9日(水) を過ぎても通知がない場合は、学会事務局(下記参照)まで電子メールにてお問い合わせ下さい。
※ 発表資格など発表応募要領をよくご確認ください。
※ 発表の内容が未発表のものであることを確認して下さい。
※ 入力内容に誤りがございますと申込手続きを進めることができませんので、ご注意ください。
※ 「申込フォーム」での送信後、登録完了のお知らせを折り返しお送りいたしますのでご確認ください。
※ ご登録いただいた個人情報は厳重に管理を行い、研究大会発表申込の手続き以外には使用いたしません。
ご自由にダウンロード・印刷・掲示ください
関西英語教育学会 2018年度(第23回) 研究大会 プログラ厶
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
主催:関西英語教育学会(KELES)
共催:大学英語教育学会(JACET)関西支部、外国語教育メディア学会(LET)関西支部
「第21回卒論・修論研究発表セミナー プログラム」について変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
日時:2018年2月11日(日・祝)
場所:関西国際大学 | 尼崎キャンパス | info 〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
参加費:会員、非会員とも 500円
※事前申込不要 当日,予稿集を配布 直接会場にお越しください
発表者の皆さまは必ずこちらをご覧ください
プログラム(PDF)のダウンロードはこちらからどうぞ(02月03日更新)
9:00 - 受付(関西国際大学・尼崎キャンパス・5階受付にお越しください) info
9:20 – 9:30 開会行事(501中講義室)
司会: 鳴海 智之(兵庫教育大学)
開会の挨拶: 里井 久輝(関西英語教育学会会長・龍谷大学)
9:40 – 11:20 午前の部 info
11:25 – 12:20 ポスター・デモ発表コアタイム info
12:20 – 13:10 昼食休憩
13:10 – 14:50 午後の部 info
14:50 – 15:35 アフタヌーン・ティー info
15:40 – 17:00 スペシャル・トーク(501中講義室) info
「外国語情意研究の視座 —WTC, L2 Self, & Community—」
講師: 八島 智子 先生(関西大学・教授)
講師紹介: 里井 久輝(龍谷大学)
17:05 – 17:15 閉会行事(501中講義室)
閉会の挨拶: 泉 惠美子(関西英語教育学会副会長・京都教育大学)
①9:40~10:10 ②10:15~10:45 ③10:50~11:20
コメンテーター:大嶋 秀樹(滋賀大学)・平井 愛(神戸学院大学)
① B: 小学校外国語活動における 韻に関する明示的・暗示的指導の効果ージャズチ ャンツを通してー/猿木 彩乃(京都教育大学)
② M: 高校におけるフォニックス指導の実証的研究/梶谷 和司(京都外国語大学)
③ M: 発音指導における訂正フィードバック—日本人英語学習者の語強勢に焦点をおいて—/多胡 夏純(神戸大学)
コメンテーター:吉田 晴世(大阪教育大学)・真崎 克彦(関西大学)
① B: 算数でのCLIL授業の実践−そろばんを使った活動を通して—/江口 明孝(京都教育大学)
② B: 子どもの貧困と英語教育機会格差の解決に向けた学校外・英語教育実践の探究/四方 翔磨(京都府立大学)
③ B: 小学校外国語活動におけるバフチンの対話原理に基づく授業実践 —称賛と応答に着目して—/湯浅 聡史(京都教育大学)
コメンテーター: 谷村 緑(京都外国語大学)・名部井 敏代(関西大学)
① B: タイ人学生・アメリカ人学生とのディスカッション時における日本人英語学習者の発話量変化/川久保 淳(関西国際大学)
② B: 問いかけがもたらす文化的豊饒化の質的研究 −バフチンの外在性の視座—/尾崎 円香(京都教育大学)
③ M: 日本人EFL話者間の協同的な対話構築における媒介物の役割/島村 彩(関西大学)
コアタイム 11:25~12:20(S1: 11:25〜11:40, S2: 11:45〜12:00, S3: 12:05〜12:20)
① B: 理解から表現へつなげるコミュニケーション英語の効果的な指導法 /河上 晃輝(関西国際大学)
② B: 日本の大学生における内発的動機づけを高めるための自己決定理論に基づくタスク中心の学習法/ 前川 尚輝(京都教育大学)
③ M: 高校英語授業でのペアワーク活動におけるAlignmentの研究:会話分析を用いて/寺崎 陽子(兵庫教育大学)
【ポスター第2室】(505演習室)
① B: EFL学習者のライティングにおける一貫性と結束性/尾野 藍子(武庫川女子大学)
② B: バフチンの対話原理に基づいた他者の応答による豊穣化の質的研究/大野 駿(京都教育大学)
③ B: SNSを利用した単語学習/森山 航太(大阪教育大学)
④ M: L2 Lexical Acquisition Through Extensive Reading Using Smartphones/田中 佑弥(大阪教育大学)
④13:10~13:40 ⑤13:45~14:15 ⑥14:20~14:50
コメンテーター: 水本 篤(関西大学)・橋本 健一(大阪教育大学)
④ B: 日本人英語学習者の英語による謝罪表現及びそれらの男女における違いについて/田中 亮次(京都外国語大学)
⑤ M:日本人英語学習者の前置詞使用の問題点の解明 —頻度・共起語・用法の 3 つの観点から—/中西 淳(神戸大学)
⑥ M: Graded Readersで使用される関係詞節の頻度と難易度:多読による文法習得に焦点を当てて /安田 直樹(関西大学)
コメンテーター:横川 博一(神戸大学)・長谷 尚弥(関西学院大学)
④ B: リーディングのプレライティング活動としての効果−コンセプトマッピングと比較して−/浦川 真緒(京都教育大学)
⑤ M: 公立中学校におけるTPRを活用した指導実践と指導効果の研究および教材開発—我が子らの言語獲得・習得過程の観察を通して—/宇田 竜子(京都外国語大学)
⑥ M: 大学でのICTを活用した協同的な多読活動の効果/森下 憲(大阪教育大学)
コメンテーター: 加藤 雅之(神戸大学)・籔内 智(京都精華大学)
④ B:創造性としてのミメーシス—EFLリーディングにおける実践—/笠井 美佳(京都教育大学)
⑤ B:テクストの深い理解に向けての読者反応理論の実践/澤田 夏来(京都教育大学)
⑥ B:ロレンスによる動物性の嘆願/杉野 久和(京都教育大学)
コメンテーター: 村田 純一(神戸市外国語大学)・溝畑 保之(大阪府立鳳高校)
④ B: 中学生によって作成されたルーブリックを活用した自己評価—自律性、自己効力感と動機付けへの効果/山村 京子(京都教育大学)
⑤ M: 高校英語授業におけるタスクの活用/濱地 亮太(関西大学)
⑥ M: 4技能を統合した指導の効果に関する研究/戸田 行彦(京都外国語大学)
講師:八島 智子 (関西大学・教授)
演題:外国語情意研究の視座 —WTC, L2 Self, & Community—
「他者と意味を共有していくプロセス」としてのコミュニケーションは、言語教育の目的であるだけでなく、最近のUsage-basedアプローチにもあるように、言語習得に必要なプロセスです。これまでコミュニケーションをコアとして外国語学習の主に情意面の研究をしてきました。今回のトークでは、前半でWTC (willingness to communicate)と国際的志向性、L2アイデンティティ(L2 self)、 コミュニティへの参加と動機付けなどの理論を概観します。後半ではこのような理論を基盤にした研究を紹介し、理論・研究・実践をどのように統合するのか、そして、外国語教育の研究は何を目指すべきなのかを考えてみたいと思います。量的研究からから質的研究へ、そして混合法へと、試行錯誤を続けてきましたが、その中で発見したことは、研究もやはりコミュニケーションだということ、つまり学習者の理解、理論との対話、そして研究コミュニティへの参加のプロセスであるということです。
● JR尼崎駅(北口)より東側遊歩道を北側へ回り込み,キューズモール東側から北側へ折れる。西へ直進し,会場校3階の入り口から,階段またはエレベータで5階受付へ。注:キューズモールは10時開店のため,朝は通りぬけできません。
学内には駐車スペースがありませんので,公共交通機関をご利用ください。
以下、発表者の皆さまに各発表形式別に簡単な注意事項を記します。(発表の形式や様子についてはこちらを参照して下さい)
発表時間:卒論 25分(15分 質疑応答 10分)、修論 30分(20分 質疑応答 10分)
パソコン:各教室にはプロジェクター(及びPC接続用のVGAケーブル)は設置されていますが,PC/Macは各自ご持参下さい。Macの場合,VGAアダプタが必要 となりますので,そちらもご持参下さい。PC/Macをお持ちでない方は,事前にセミナー担当者に問い合わせて下さい。
AV機器:CDやDVDの使用は可能です。MDやカセットは不可。
会場下見:発表会場の下見、パワーポイントスライドのテスト等は、午前の部の方は、開会行事後から第1発表の間までの時間に、午後の部の方は、昼食休憩の間に、各自で行ってください。
発表資料:予稿集・プレゼンテーションスライド(任意) 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
コアタイム: 11:25 ~12:20の間は,必ず各自の持ち場に待機して下さい。その間,11:25〜11:40,11:45〜12:00,12:05〜12:20,の各回15分のセッションにて,参会者に説明や質疑を行って下さい。
ポスター:【サイズ】最大A0までにて作成。(一枚ものでも,A4を組み合わせても可)【貼付け】ボードまたは壁に貼付け。貼付けに必要な資材は,学会事務局で準備します。【掲示時間】9:30~13:20
パソコン: PC/Macは各自ご持参下さい。
AV機器: PCから音声を出す場合,ポータブルスピーカー等は各自ご持参下さい。その他,CDやDVD等のご使用については,学会事務局にお問い合わせ下さい。
什器: 長机やイスは発表スタイルに応じて準備しますので,学会事務局にお尋ね下さい。発表資料:予稿集・ポスター 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
プログラム(PDF)をダウンロードいただけます。以下の表紙をクリックして下さい(別ウィンドウ)
2018年02月○日公開
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
TEL: 078-803-7684 [dial-in]
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
日時:2018(平成30)年2月11日(日・祝)9:30~17:30
会場:関西国際大学 尼崎キャンパス → アクセス
〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
内容:学部学生による卒業論文・大学院生による修士論文の研究発表(口頭発表またはポスター発表)
コメンテーター:主催・共催学会に所属する教員・研究者
プログラムは作成され次第 こちら でアナウンスします。(2月3日更新)
関西英語教育学会では、大学英語教育学会(JACET)関西支部,外国語教育メディア学会(LET)関西支部との共催で,本年度も下記の要領で「卒論・修論研究発表セミナー」を開催致します。お忙しい時期とは存じますが、多くのご発表ならびにご参加を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
 講師:八島智子先生(関西大学)
講師:八島智子先生(関西大学)
プロフィール:八島智子(やしまともこ):関西大学外国語学部・大学院外国語教育学研究科教授。博士(文化科学、岡山大学)。専門は応用言語学と異文化間コミュニケーション論。主な著書に「外国語コミュニケーションの情意と動機」(関大出版会)「異文化コミュニケーション論:グローバル・マインドとローカル・アフェクト」(松拍社)。主な論文に、“Willingness to communicate in L2: The Japanese EFL context.” (2002) The Modern Language Journal, “Influence of attitudes and affect on willingness to communicate and L2 communication.” (2004). Language Learning、 またDörnyei & Ushioda (eds.) (2009) Motivation, language identity and the L2 self (Multilingual Matters)、Dörnyei et al. (eds.) (2013) Motivational Dynamics in Language Learning (Multilingual Matters)、Mercer et al.(eds). Psychology for language learning (Palgrave)などにも論文を掲載している。詳しくはhttp://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/%7Eyashima/
演題:「外国語情意研究の視座 —WTC, L2 Self, & Community—」
概要:「他者と意味を共有していくプロセス」としてのコミュニケーションは、言語教育の目的であるだけでなく、最近のUsage-basedアプローチにもあるように、言語習得に必要なプロセスです。これまでコミュニケーションをコアとして外国語学習の主に情意面の研究をしてきました。今回のトークでは、前半でWTC (willingness to communicate)と国際的志向性、L2アイデンティティ(L2 self)、 コミュニティへの参加と動機付けなどの理論を概観します。後半ではこのような理論を基盤にした研究を紹介し、理論・研究・実践をどのように統合するのか、そして、外国語教育の研究は何を目指すべきなのかを考えてみたいと思います。量的研究からから質的研究へ、そして混合法へと、試行錯誤を続けてきましたが、その中で発見したことは、研究もやはりコミュニケーションだということ、つまり学習者の理解、理論との対話、そして研究コミュニティへの参加のプロセスであるということです。
参加費:会員、非会員とも 500円(当日、予稿集を配布)
プログラム内に,アフタヌーンティーを設定する予定です。発表者・コメンテーターや講師の先生方,参会者の皆さまとの気軽な交流の時間です。
上記の内容につきまして、変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
発表資格:学部生・院生(発表者は学会員である必要はありません)
申込期間:2017年12月16日(土)〜2018年1月22日(月)まで【厳守】
発表分野:外国語教育,外国文学,言語学および関連分野
発表形式:口頭発表またはポスター・デモ発表(発表申込時に発表形式の希望をお尋ねしますが,発表者数によっては,口頭↔ポスター・デモ発表に変わっていただくこともございます)(発表形式についての詳細は,前回の様子をご覧下さい こちら)
発表時間:
<口頭発表>卒業論文25分(発表15分,コメント・質疑応答10分)・修士論文30分(発表20分,コメント・質疑応答10分)
<ポスター・デモ発表>卒業論文・修士論文とも掲示・質疑(コアタイム45分:15分×3セット)
使用言語:日本語または英語
予稿集:発表者の方には,2018年1月29日(月)までに,予稿集原稿(A4用紙2ページ以内)をご提出いただきますのであらかじめご承知おき下さい。発表者の方にはテンプレートをお送りします。
発表申込方法:第21回卒修論セミナーホームページ【申込フォーム】より,必要事項(発表言語での論文タイトル・キーワード(3~5語)・日本語200字程度, 英語400 words程度の発表要旨を含む)を入力・送信してください。
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「言語教育にとってのタスク、言語教師にとってのチャレンジ」
松村昌紀 先生(名城大学)
14:40-16:00 「TBLTの課題・展望・指導の工夫」
田村祐 先生(名古屋大学大学院)
16:00-17:20 「タスク・ベースのマインド・セットで21世紀を楽しむ」
溝畑保之 先生(大阪府立鳳高等学校)
17:20-17:50 講師同士のセッション・フロアとのQ & A セッション
17:50-17:55 閉会のことば
 【プロフィール】
【プロフィール】松村昌紀(まつむらまさのり):三重県立高等学校教員として勤務の後、愛知県、神奈川県内の大学を経て、現在名城大学理工学部で英語科目を担当;研究領域は第二言語習得、特に言語発達における手がかり(学習可能性)の問題;著書に『英語教育を知る58の鍵』(大修館書店, 2009年)など、翻訳書として『タスクが開く新しい英語教育──英語教師のための実践ハンドブック』(共訳, 開隆堂出版, 2003年; 原著 A Framework for Task-Based Learning by Jane Willis)
現代の言語教育の文脈で「タスク」と呼ばれるコミュニケーション課題の特性や効果をめぐっては、さまざまな角度から研究や議論が重ねられてきました。国内でも、今後の英語教育のあり方との関連でそれらの活用に関心が持たれる一方、その輪郭が理解しにくいという声も聞かれます。それをふまえて、お話では最初にタスクを6つのタイプに整理し、実例を交えながらそれぞれに特徴的な性格、および目的に応じて変えることのできる側面についてて説明します。 その後、タスクの活用が英語の指導や学習に対する考え方やその中身をどのように変えていくことができるか、そしてその受け入れのために英語教員にはどのような発想の転換が必要になるのかを検討してみます。お話は中等教育(中学校、高等学校)での指導を念頭に置いたものになりますが、小学校、大学での英語指導にも活かせる内容を含めたいと思います。
 【プロフィール】
【プロフィール】田村祐(たむらゆう):名古屋大学大学院博士課程後期課程在籍,日本学術振興会特別研究員(DC2),愛知工科大学非常勤講師;研究領域は,第二言語の文法習得や文処理。分担執筆書として『タスク・ベースの英語指導ーTBLTの理解と実践』(松村昌紀編著,大修館書店,2017年),主な論文として,/Unconscious but slowly activated grammatical knowledge of Japanese EFL learners: A case of tough movement /(共著,ARELE, 2016年)などがある。
本講演では,タスク・ベースの英語指導を実践していく上での課題を,教科書・文法シラバス・評価,という3つの観点から見ていきたいと思います。タスク・ベースの指導は,いつ,どこでも,どんな学習者を相手にしても,必ずうまくいく「魔法のような指導」というわけではありません。おそらく,そのような唯一無二の指導というのは存在しないだろうということは,多くの言語教師の方々が身をもって感じていることでしょう。しかし,どのような状況においても柔軟に指導を変化させることができるという利点がTask-based Language Teaching (TBLT)にはあります。この点を念頭におき,TBLTを実践しようとしたときに懸案事項となるであろう,教科書・シラバス・評価という3つの点を取り上げ,それをどのように乗り越えていくことが可能かどうか検討します。最後に,指導上の工夫で乗り越えられることと,教師自身の発想の転換が必要になることなどに論点を分けていきながら,TBLTの実践がどのような変化をもたらすかなどの展望について考えてみたいと思います。
 【プロフィール】
【プロフィール】溝畑保之(みぞはたやすゆき):大阪府立鳳高等学校教諭(平成28年まで府立学校指導教諭);38年の教職を通して4技能の統合をめざした実践を行ってきている;1980年代のCommunicative Language Teachingの精神を、日本独自の英語教育の枠組みで活かす方策を探ってきた;『英語指導ハンドブック』シリーズ(語彙2005,リーディング2008,音読2010,スピーキング2017,大修館書店)でその事例を紹介している;論文及び研修会,英語教育達人セミナー,その他各学会で口頭発表多数
平成27年度より、現任校英語科でICT機器を活用したアクティブ・ラーニング(AL)の取組「フェニックス・プロジェクト」を推進し、今年で3年目となります。具体的には、CLIL、ICEモデル、ジグソー法、KP法、ミニ・パーラメンタリー・ディベート、多読など、様々な手法を用いて、4技能統合型授業に取り組んでまいりました。今、21世紀型の教育をめざし、他教科でのALが広がっているなか、英語科では形式的なペア活動(CLT)で終始し、真正のALが行われていないのではないでしょうか。ALで大切にしたい「協調精神」を、英語教育は尊重してこれているのでしょうか?実践を通して、ロング(2015)によるタスク・ベースの中心的原理のひとつが、「相互扶助と協同」であることを実感しています。この2年間の実践をTBLの観点から報告します。一点刻みで選別のみ優先の入試が変わろうとしています。授業と評価の一体化の精神を踏まえ、4技能入試導入と一連の授業改善を議論の足場にし、教員のマインド・セットについても提案したいと考えています。
KELES 第43回セミナーご案内 (PDF)
下記のフォームをご利用ください(11月19日より受付開始)
第43回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「日本人による英語音声の知覚・発声と学習:日本人は英語音声の知覚・発声がなぜ難しく,どう学習すべきか」
湯澤正通 先生(広島大学)
14:40-16:00 「文字から音へ,音から文字へ」
川崎眞理子 先生(関西学院大学)
16:00-16:40 講師同士のセッション・フロアとのQ & A セッション
16:40-16:50 閉会のことば

1992年 広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了(博士(心理学))
現在 広島大学大学院教育学研究科教授
専門
教育心理学,発達心理学,学習心理学
最近の主要著書
湯澤美紀・湯澤正通・山下 桂世子・藤堂 栄子『ワーキングメモリと英語入門: 多感覚を用いたシンセティック・フォニックスの提案』北大路書房 2017年8月
湯澤正通・湯澤美紀『ワーキングメモリを生かす効果的な学習支援: 学習困難な子どもの指導方法がわかる!』学研プラス 2017年7月
湯澤正通・湯澤美紀(編著)『ワーキングメモリと教育』北大路書房 2014年
湯澤正通・湯澤美紀『日本語母語幼児による英語音声の知覚・発声と学習: 日本語母語話者は英語音声の知覚・発声がなぜ難しく,どう学習すべきか』風間書房 2013年
湯澤美紀・河村 暁・湯澤正通『ワーキングメモリと特別な支援: 一人ひとりの学習のニーズに応える』北大路書房 2013年
日本人はどうして英語が苦手なのでしょうか。英語を勉強したことのない中国人幼児と日本人幼児に,英単語を聞かせて,聞いたまま反復してもらいます。すると,中国人幼児の方がずっとよくできます。しかし,最初の音は何でしたかと聞くと,日本人幼児の方が正しく答えられます。このことは,中国人大学生と日本人大学生を比較しても同じです。日本人は,日本語の影響のため,英語の音を細かく分析するため,英語の音をなめらかに聞き取ることができません。英語の音を細かく分析すると,ワーキングメモリに過大な負荷がかかります。例えば,”send”は1音節なので,英語母語話者は一つの情報のまとまりとして知覚します。それを「センド」と知覚すると,3モーラの3つの情報のまとまりになります。当然,1つよりも3つの情報のまとまりの方がワーキングメモリに負荷がかかります。こうした英語音声の分節化を日本人幼児が行っていることを示した研究データを紹介します。そして,そのような分節化が,6年以上,英語を学習した日本人大学生においても見られることを示します。
 【プロフィール】
【プロフィール】プロフィール:関西学院大学・人間福祉学部教員,関西学院大学大 学院修了,言語コミュニケーション文化学博士。研究分野はディコーディング,早期英語教育,シャドーイングや音読時の脳内処理や英語学習への効果のしくみ。児童~ 成人対象の英語教室を自営しながら,企業で教えていましたが,長年蓄積した疑問点を解明したくて大学院に進学し,そのまま研究にはまりました。2013年から小学校でのモジュール学習の支援をさせていただき,観察や研究 の必要性を再認識できました。英語学習が苦手になってしまった人に寄り添うこと,今後できる限りそのような人を生み出さないようにすることが私に与えられた役割です。 著書:門田修平・鈴木寿一編著「英語音読指導ハンドブック」(2012)大修館書店のフォニックス関連部分
「これどう読むんですか」と尋ねられたことはありませんか。その単語の綴りが基本的規則に従っていたりしませんか。逆に,完全に不規則な綴り(読み方)の単語を,規則を適用して読んでしまった人が,笑われたり,叱責されたりした場面に遭遇したことはありませんか。自分の力で未知の文字列を音にできる学習者を育てるためには,文字との豊富な接触経験と,文字と音の対応知識が不可欠です。日本語の識字と英語の識字との相違点を踏まえて,効果的な学習・指導方法を考えたいと思います。
KELES 第42回セミナーご案内 (PDF)
下記のフォームをご利用ください(10月16日より受付開始)
第42回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「いろんな視点から見てみよう:英語教育研究に取り組む皆さんとの第一歩」
橋本健一 先生(大阪教育大学)
14:40-16:00 「我々はなぜ論文を読むのか、どう読めばいいのか、読んでどうするのか」
亘理陽一 先生(静岡大学)
16:00-16:40 講師同士のセッション・フロアとのQ & A セッション
16:40-16:50 閉会のことば
本セミナーに参加の皆さまは,事前に以下の論文を読んでいただきたいと思います。いずれもダウンロード可能です(1は以下の注をご確認下さい)。
1) Good, A. J., Russo, F. A., & Sullivan, J. (2015). The efficacy of singing in foreign-language learning. Psychology of Music, 43, 5, 627–640. http://doi.org/10.1177/0305735614528833 (ジャーナルの該当ページはこちら)
2) Richards, J. C., & Reppen, R. (2014). Towards a pedagogy of grammar instruction. RELC Journal, 45, 1, 5-25. doi: 10.1177/0033688214522622(こちら)
3) Sugai, K., Yamane, S., & Kanzaki, K. (2016). The time domain factors affecting EFL learners’ listening comprehension: a study on Japanese EFL learners. ARELE, 27, 97-108.(こちら)
(注 論文1については,アクセス権がなければ見れない場合があります。その場合は,事務局までご連絡下さい。)
 【プロフィール】
【プロフィール】大阪教育大学教育学部准教授。神戸大学大学院総合人間科学研究科修士課程,クイーンズランド大学博士課程修了(PhD取得)。近畿大学農学部特任講師,同講師を経て,2014年より現職。専門は第二言語における心理言語学と英語教育学。第二言語・外国語における文理解プロセスを明らかにすること、そこから得られた知見が英語教育にどう活かされるかという点に関心がある。主な著作として,横川博一・定藤規弘・吉田晴世(編著)『外国語運用能力はいかに熟達化するか:言語情報処理の自動化プロセスを探る』(共著,松柏社),吉田晴世・加賀田哲也・泉恵美子(編著)『英語科・外国語活動の理論と実践』(共著・あいり出版),Syntactic processing of L2 English relative clause sentences: The effect of proficiency(ARELE, 2010年)などがある。
授業であっても、研究であっても、あるいは事務仕事であったとしても、「これで100点満点!」ということは(少なくとも私は)ほとんどありません。場面・内容・人が変わればやり方も変わる。校種を問わず教員(研究者)には、考えてより良い一手を見出す力が今まで以上に求められていると思います。
教員養成系大学である本学にも、英語教育について専門的に勉強したいという学生・院生が多く来てくれます。より良く考えられる教員、そして英語教育の研究者への第一歩として、私は学生・院生が自身の興味・関心のある分野以外のエリアへ視野を広げてもらうことに積極的であってもらいたいと思っています。本トークでは、「視野を広げる」というゴールに向けた私自身の試行錯誤を中心にお話したいと思います。私自身は第二言語における心理言語学、特にことばを理解する際の心的プロセスについての研究をしていますが、いろいろなバランスに苦心しながら、そのような見方を導入していくことから始まり、学生・院生同士のインタラクションにつながりつつある事例や、私自身が院生だったころの視野の狭さ故の失敗談などもお話できればと思います。
本トークが、これから英語教育研究を始めてみようという皆さんの第一歩になれば嬉しいですし、私自身が「より良い指導者」になりたいと願う一人として、亘理先生やオーディエンスの皆様とのインタラクションを楽しみにしています。
 【プロフィール】
【プロフィール】静岡大学教育学部准教授。北海道大学教育学研究科博士後期 課程修了。博士(教育学)。静岡理工科大学教育開発センター特命講師,同総合情報学部講師,静岡大学教育学部講師を経て 2015 年より現職。専門は,英語教育学・教育方法学。文法指導の目的・内容・方法を中心とする、カリキュラム編成・授業実践・教師教育研究に関心がある。近年の著作に,『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ: 小学校外国語科内容論』(共編著,三省堂), 『はじめての英語教育研究: 押さえておきたいコツとポイント』(共編著,研究社),『高校英語授業を知的にしたい: 内容理解・表面的会話中心の授業を超えて』(共編著,研究 者),『学習英文法を見直したい』(共著,研究社)などがある。
研究者は日々、論文を漁り、読んでいます(そのはずです)。仕事の一環だと言えばそれまでですが、なぜ、何を読むのか。先人は「読書百遍意自ずから通ず」と言うかもしれませんが、忙しい学生・院生からすれば、どこに注目してどう読めばいいのかを示して欲しいのが正直なところでしょう。指導教員の側から言えば、「まず100本、200本読みましょう」と言ったところで、学生・院生が論文を読んでくれるわけではありません。かといって、1本読んでその内容を絶対視したり、特定の著者を盲信されても困る。そもそもどこから、どういう論文を見つけてもらえばいいのか。指導教員の悩みは尽きません。本セミナーでは、「英語教育研究事始め」として、論文の探し方・集め方から始め、具体的な論文の講読を通じて読み方のポイントを示し、教員養成系大学で学生・院生に論文を読んでもらうための私自身の試行錯誤を紹介します。それを通じて考えたいのは、学生・院生、現職教員が論文を読む目的です。卒論・修論が書き上がってしまえば、もう論文は読まなくていいのか。もちろん、私はそうは思いません。関心の裾野を広げ、研究を診る目を鍛えた上で、必要を感じたらいつでも自分のために「論文を読む」という選択肢を持った人を送り出したい。橋本先生、そしてみなさんとゼミのように意見を交わすことができれば幸いです。
下記のフォームをご利用ください(9月11日より受付開始)
第41回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
LET関西2017年度春季研究大会・2017年度関西英語教育学会(KELES)第22回研究大会(共催) 特別シンポジウム「明示的指導の理論と実践:発音・語彙・文法指導への可能性」の動画を公開しました。以下のリンク(LET関西のYoutubeチャンネル)より、是非ご覧ください。
LET関西2017年度春季研究大会・2017年度関西英語教育学会(KELES)第22回研究大会(共催)を下記の要領で開催致します。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
外国語教育メディア学会(LET)関西支部・関西英語教育学会(KELES)
研究大会共催趣意書(pdf)
→ プログラムのダウンロード
→ アブストラクトのダウンロード
2017 (平成 29) 年
6 月 10日(土)9:40~17:45(9:30受付開始)
6 月 11日(日)9:30~16:25(9:00受付開始)
近畿大学・東大阪キャンパス
〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1 → アクセス
関西英語教育学会会員・LET関西会員:無料
非会員 (一般):2,000 円
非会員 (学部学生・大学院生):1,000 円
*学生証をご提示下さい。提示がない場合は一般参加費となります。
*事前申込の必要はございません。当日会場にお越し下さい。
*上記参加費で2日間ご参加いただけます。会場では名札をご使用下さい。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
「学生の携帯端末を授業に活用する方法」【LET関西企画】
岩居弘樹(大阪大学)
「英語論文を書いて国際ジャーナルに掲載させるためのストラテジー」【LET関西企画】
水本篤(関西大学)・斎藤一弥(ロンドン大学)
「『アクティブ・ラーニング』から『主体的・対話的で深い学び』へ—本当に大切なことは何かを考える—」【KELES企画】
中井弘一(京都橘大)
① 11:45~12:05 ② 12:05~12:25 ③ 12:25~12:45
① 生徒の意見を電子ファイル/掲示物として一気にまとめる方法/真島 由朱(大阪府立箕面高等学校)
② Kahoot!で簡単クイズを作ってみよう/長谷川 由美(近畿大学)
③ 360 度カメラを使った授業記録と振り返り/矢野 浩二朗(大阪工業大学)
○ 昼食は,学内の食堂,または大学周辺の飲食店をご利用ください。
○11:45~12:45 の間,LET 関西支部の運営委員会が202 教室にて開催されます。
○12:50~13:25 の間,LET 関西支部の支部総会が301 教室にて開催されます。
①13:30~14:00 ②14:10~14:40 ③14:50~15:20
① 【招待発表】Effects of Implicit and Explicit Form-focused Instruction on
Low-Intermediate Learners’ Grammar Acquisition/Natsuko Shintani(The University of Auckland)
② 高校でのMoodle を使用した反転授業の実践報告/上田 愛(大阪府立長野高等学校)・篠崎 文哉(大阪教育大学附属天王寺中学校)・上田 瑠璃(大阪教育大学 大学院生)
③ ラウンド制授業により検定教科書を徹底多聴多読させた1 年間の実践発表:共有
出来る読解聴解対応力養成授業の普及を目指して/幸前 憲和(株式会社クロスインデックス)
① 【招待発表】分散学習は意味的に関連した単語の習得を促進するか?:干渉効果と
分散効果の検証/中田 達也(関西大学)・鈴木祐一(神奈川大学)
② 会話相手によるL2 WTC の変化について:L2 能力の異なる学習者群の比較から/鎌田 理星(関西大学 大学院生)
③ 日本の高校生のデジタル媒体「宿題」に関する認知:Cengage Learning- MyELT
を使用した混合研究法調査/小島 修司(啓明学院中学校高等学校,テンプル大学PhD. Candidate)
① 【招待発表】英語論文執筆支援ツールAWSuM の有用性の検討―パイロット・ス
タディ―/水本 篤(関西大学)
② 日本語母語話者が持つ音象徴の感覚:架空キャラクターのネーミング調査から/中西 のりこ(神戸学院大学)
○司会 小山 敏子(LET 関西支部副支部長・大阪大谷大学)
○挨拶 泉 惠美子(関西英語教育学会副会長・京都教育大学)
○参加費は,一般2,000 円,学生1000 円です。
○当日,受付にてお申し込みください。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
○第1日目にご参加された方は,名札を付けて入場下さい。
めっちゃ楽しい!「即興的やりとり」のためのアクティビティ紹介
三野宮 春子 (大阪桐蔭女子大学)
伊藤 仁美 (愛徳学園中学・高等学校)
主体的?対話的?深い学び?こんな実践はいかがでしょう。ーミハイル・バフチンー
西本 有逸 (京都教育大学)
質的研究入門―実践研究に役立てるために
高木 亜希子 (青山学院大学)
生徒が自ら学びを選択する場づくり~多種多様なプロジェクトで意欲・個性・絆が育つと、進度・種類が豊富なメニューで自律的に学び出す~
江藤 由布 (近畿大学附属高等学校・一般社団法人オーガニックラーニング代表理事)
① 13:00~13:30 ② 13:35~14:05 ③ 14:10~14:40 ④ 14:45~15:15
① 事例報告:神戸大学附属中等教育学校英語評価尺度(KUSF)の開発プロセスの紹介̶—能力記述文の継続的な検証と修正を踏まえて̶—/増見 敦(神戸大学附属中等教育学校)
② 事例報告:小学校英語教育実施に向けての現状と課題克服に向けて̶—小学校現場での取り組みにおける苦闘から明るい未来へ̶—/高木 浩志(宝塚市立逆瀬台小学校)
③ 研究発表:協働ライティング遂行時の対話分析̶—母語使用とタスクタイプの影響—/新田 奈央(J 国際学院 非常勤)
④ 研究発表:ライティング教育における語句整序問題に関する一考察̶—同一日本語文を扱った語句整序問題と英訳問題をもとにして̶—/橋尾 晋平(同志社大学 大学院生)
① 事例報告:英語習熟度最下位クラスにおけるスピーキングによる学習振り返り̶理解が深まる授業を目指して̶—/牧野 眞貴(近畿大学)
② 研究発表:-ing 形節:「分詞構文」に代わる新しい文法用語秦/正哲(兵庫医療大学)
③ 事例報告:The case study of communicative language teaching: Completing
the task by communicating with each other/小越 裕史(神戸市外国語大学 大学院生)
① 事例報告:学習者の意欲を引き出す導入—授業̶認知スタイルの観点をふまえた一考察̶—/井上聡(環太平洋大学)
② 研究発表:英語発話時と日本語発話時の眼球運動の比較についての一考察—スピーキング指導法開発を目指して—/片野田 浩子(四天王寺大学)・クリス西浜(CKD(株))
③ 研究発表:4技能統合を目指す「アクティブ・ディクトグロス」の提案/西村 嘉浩( )
① L2 使用とクラスルームの活性化̶—2つの中学校の授業観察から̶—/中野 里香(関西大学大学院)
② Unfocused Task での学習者の気づき/濱地 亮太(関西大学大学院)
③ 日本留学中の日本語学習者の英語学習ニーズに関する考察/辻本 桜子(立命館大学)
○関西英語教育学会事務局長 挨拶 大和 知史(神戸大学)
○LET 関西支部副支部長 挨拶 山本 勝巳(流通科学大学)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2017年度(第22回) 研究大会 プログラム(PDF)
5月1日公開(11日最新版)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2017年度(第21回)研究大会 研究発表・公募フォーラム・アブストラクト(PDF)(5月11日 最新版)
関西英語教育学会2017年度(第22回)研究大会 講演・セミナー・ワークショップ等アブストラクト(PDF)(5月10日 最新版)
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
2017年度関西英語教育学会(第22回)研究大会を下記の要領で開催致します。
今回の研究大会は,外国語教育メディア学会関西支部(LET関西)との共催にて,6月10日(土),11日(日)の2日間,近畿大学東大阪キャンパスにて研究大会を開催することとなりました。
関西英語教育学会の会員の皆さまにおかれましては,これまで通り,研究発表・事例報告を行っていただけますとともに,LET関西との共同企画やLET関西の企画を中心とした1日目に参加していただけます。
今回も,研究発表・事例報告に加えて,公募ワークショップ・公募フォーラムの発表募集を行います。奮ってご応募下さい。多くの皆様のご発表・ご参加をお待ちしております。
2017(平成 29) 年 6 月 10日(土)・11 日 (日)
近畿大学東大阪キャンパス アクセス
関西英語教育学会会員:無 料
非会員(一般):2,000 円
非会員(学部学生・大学院生):1,000 円 (※学生証を提示して下さい)
- 開会行事
- ワークショップ【KELES企画・LET関西企画】
- 自由研究発表【LET関西会員による】
- Classroom Tips【LET関西会員による】
- シンポジウム【KELES・LET関西共同企画 】「明示的指導の理論と実践:発音・語彙・文法指導への可能性」
- レセプション【KELES・LET関西】
- 公募ワークショップ/公募フォーラム【KELES会員による】
- ブランチor ランチョン セミナー【KELES企画】
- 研究発表・事例報告(口頭発表・ポスター・デモ発表)【KELES会員による】
- 講演【KELES企画】
発表者は、関西英語教育学会の会員にかぎります。
※LET関西の会員で,1日目のLET関西企画の自由研究発表やTeaching Tipsに発表をご希望の方は,LET関西の大会ウェブサイトより別途申し込み下さい。
※両学会の会員である場合,両方に発表を申し込むことは可能です。
※ 2017 年 4 月 21 日(金)までに,会員の方は 2017 年度の学会費を納入していることが必要です。非会員の方は、会員手続き(入会申込および会費納入)を済ませて下さい。入会手続きおよび会費納入が確認されない場合は、発表自体が取り消しとなりますのでご注意下さい。
※ 共同研究者は学会員であることが望ましいですが、必ずしも会員である必要はありません。ただし、当日の発表は学会員が行って下さい。
広く英語教育にかかわる理論的・実証的研究および授業実践に関する報告で、未発表のものに限ります。
日本語または英語
(1)研究発表 (理論的、実証的研究の発表)
(2)事例報告 (授業実践に関する報告)
(3)ポスター・デモ発表(ポスター発表・対面発表・教材教具などのデモなど)
(4)公募ワークショップ(1人または複数の講師による英語授業実践をテーマとした企画)
(5)公募フォーラム(コーディネータおよび数名の英語教育にかかわる理論的・実証的研究をテーマとした企画)
(1)口頭発表(1 件につき発表 20 分、質疑応答 5 分〜10分* プログラム構成によって質疑の時間の若干の変動あり)
(2)ポスター・デモ発表(発表コアタイム 60 分)
(3)公募ワークショップ・公募フォーラムは1件あたり90分です。
本ページの申込フォームから、必要情報(以下の内容)を入力して送信して下さい。
2017 年 3 月 31 日(木) ~ 4 月 21 日(金) 23:59 まで
※期限厳守。期限を過ぎたものはいかなる理由があっても受け付けることができませんので,留意して下さい。
2017 年 4 月 28 日(金) までに登録されているメールアドレス宛てに、電子メールにて通知します。
※4 月29日(土) を過ぎても通知がない場合は、学会事務局(下記参照)まで電子メールにてお問い合わせ下さい。
研究発表・事例報告・ポスター・デモ発表・公募フォーラム・公募ワークショップは,大会2日目に予定されています。なお,時間帯の指定はご遠慮下さい。
※ 発表資格など発表応募要領をよくご確認ください。
※ 発表の内容が未発表のものであることを確認して下さい。
※ 入力内容に誤りがございますと申込手続きを進めることができませんので、ご注意ください。
※ 「申込フォーム」での送信後、登録完了のお知らせを折り返しお送りいたしますのでご確認ください。
※ ご登録いただいた個人情報は厳重に管理を行い、研究大会発表申込の手続き以外には使用いたしません。
ご自由にダウンロード・印刷・掲示ください
関西英語教育学会 2017年度(第22回) 研究大会 プログラ厶
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
主催:関西英語教育学会(KELES)
共催:大学英語教育学会(JACET)関西支部、外国語教育メディア学会(LET)関西支部
「第20回卒論・修論研究発表セミナー プログラム」について変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
日時:2017年2月12日(日)
場所:関西国際大学 | 尼崎キャンパス | info 〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
参加費:会員、非会員とも 500円
※事前申込不要 当日,予稿集を配布 直接会場にお越しください
発表者の皆さまは必ずこちらをご覧ください
プログラム(PDF)のダウンロードはこちらからどうぞ(02月03日更新)
9:00 - 受付(関西国際大学・尼崎キャンパス・5階受付にお越しください) info
9:20 – 9:30 開会行事(501中講義室)
司会: 鳴海 智之(兵庫教育大学)
開会の挨拶: 里井 久輝(関西英語教育学会会長・龍谷大学)
9:40 – 11:20 午前の部 info
11:25 – 12:20 ポスター・デモ発表コアタイム info
12:20 – 13:15 昼食休憩
13:15 – 14:45 午後の部 info
14:50 – 15:35 アフタヌーン・ティー info
15:40 – 17:00 スペシャル・トーク(501中講義室) info
「外国語運用能力はいかに熟達化するか—言語情報処理の自動化プロセスを探る」
講師: 横川 博一 先生(神戸大学・教授)
講師紹介: 里井 久輝(龍谷大学)
17:05 – 17:15 閉会行事(501中講義室)
閉会の挨拶: 泉 惠美子(関西英語教育学会副会長・京都教育大学)
①9:40~10:10 ②10:15~10:45 ③10:50~11:20
コメンテーター:吉田 晴世(大阪教育大学)・大嶋 秀樹(滋賀大学)
① B: 小学校英語教育における絵本を用いた指導の効果/中尾 真奈子(京都教育大学)
②B: 小学校英語における効果的な語順指導—絵本や明示的指導を通して/川辺 裕菜(京都教育大学)
③M: 日本人英語学習者におけるトップダウン・ボトムアップシャドーイングのリズム習得の効果:教材難易度の影響/大谷 侑生(関西学院大学)
コメンテーター:能登原 祥之(同志社大学)・水本 篤(関西大学)
① B: 語彙の頻度に基づく効果的な学習方法/梶川 舞(京都教育大学)
②M: Assessment of the effect of mnemonics on vocabulary learning: A study on a Chinese vocabulary learning resource/王 彰(立命館大学)
③M: Creating self-report receptive vocabulary knowledge profile/伊藤 仁美(神戸市外国語大学)
コメンテーター: 籔内 智(京都精華大学)・谷村 緑(京都外国語大学)
①B: 英語の移動動詞(come/go)のダイクシスについて/比嘉 遥(摂南大学)
②M: 母語を利用した前置詞underの言語産出指導とその効果/黒川 智尋(広島修道大学)
③M: 英語ライティングへの訂正フィードバックの効果‐日本人大学生の冠詞の誤りと習得の関連‐/加藤 充(立教大学)
コアタイム 11:25~12:20(S1: 11:25〜11:40, S2: 11:45〜12:00, S3: 12:05〜12:20)
①B: 文脈を用いた語彙学習アプリケーションの開発: Androidアプリ『テキスト英単語』/村木 奏介(関西大学)
②B: 日本人大学生英語能力上位群と下位群間で使用されている語彙学習方略の違い/上野 将太郎(関西国際大学)
③M: 日本人英語学習者の英語熟達度が自由英作文の評価に与える影響/大西 潮音(兵庫教育大学)
④M: Reported language learning strategies in an EFL context: What language learning strategies do Chilean students from two different contexts report using?/ガラス セゲル ハビエラ(立命館大学)
【ポスター第2室】(505演習室)
①B: 小学校英語教育における発音導入法/土田 翔太 (関西国際大学)
②B: 英語教育における小学校と中学校のギャップ研究/冨 祐磨(関西国際大学)
③M: 社会認知的アプローチからみた外国語活動におけるインタビュー活動の分析/鎌田 奏(兵庫教育大学)
④M: インプロを通した外国語活動の学び —児童の相互行為から創造される意味—/藤井 伸子(兵庫教育大学)
④13:15~13:45 ⑤13:50~14:10 ⑥14:15~14:45
コメンテーター: 中田 賀之(同志社大学)・名部井 敏代(関西大学)
④B: スピーキングにおける不安の軽減の試み -ネイティブスピーカーとの定期的なビデオチャットを通して-/大柿 敦(京都教育大学)
⑤B: 第二言語学習における肯定的心理の観点からみた動機づけと英語能力との相関/沖 圭介(京都教育大学)
⑥M: 英語学習者と協働的に行うインタビューにおけるダイナミックアセスメント/大和 智子(兵庫教育大学)
コメンテーター:吉田 信介(関西大学)・佐々木 顕彦(武庫川女子大学)
④M: マルチメディアCALL教材と多読が高校生の英語読解力に与える効果—公立高校での実践的研究—/杉本 喜孝(立命館大学)
⑤M: Measuring the effects of an online learning community on the listening, speaking, reading and writing skills of Japanese EFL learners/三宅 建(大阪教育大学)
⑥M: Teachers’ attitudes towards ELT textbooks in the digital age: A comparative study between pre-service and in-service teachers in Japan and China/石 佳(大阪教育大学)
コメンテーター: 加藤 雅之(神戸大学)・吉田 真美(京都外国語大学)
④M: 定型・非定型連鎖のアクセスに音読トレーニングが与える影響:日本人英語学習者における実証研究/西村 浩子(関西学院大学)
⑤M: 日英翻訳の神経心理学的考察に向けての研究: 機械翻訳と人間の手による翻訳に感じる相違感について/岡本 吉世(滋賀大学)
⑥M: ランゲージングの効果—文学テクストの深い理解を目指して/岡林 洋平(京都教育大学)
コメンテーター: 村田 純一(神戸市外国語大学)・加賀田 哲也(大阪教育大学)
④B: 英語教育における「知の理論」の可能性—ライティング活動の事例—/西田 有里(京都教育大学)
⑤M: A Study on the Effectiveness of CLIL-oriented English Classes at Primary Schools in Japan/松延 亜紀(京都教育大学)
⑥M: 日本の英語教育における小中連携の在り方/渡邊 博三(滋賀大学)
講師:横川 博一 (神戸大学・教授)
演題:外国語運用能力はいかに熟達化するか—言語情報処理の自動化プロセスを探る
今,日本の英語教育は抜本的改革を迫られているように思います。英語教育を取り巻く動きには枚挙にいとまがありません。教育のパラダイム転換の動きと相まって声高に英語 教育改革が叫ばれる背景にあるのは,英語運用能力の育成と向上に対する強い期待と要請と言ってよいでしょう。
英語運用能力の育成には,運用能力の基盤となる知識の形成と運用スキルの習熟を図ることが必要であり,言語処理の自動化が英語運用能力の熟達化にとって重要な役割を果たします。しかし,その認知メカニズムは十分に明らかにされているとは言い難く,その認知メカニズムを解明することが,英語運用能力育成のカギともなります。
このトークでは,これまでのおよそ30年を振り返って,英語教育・心理言語学との出会いから,私自身の失敗と試行錯誤の連続としての授業実践も踏まえ,最近の科研プロジェクトで取り組んできた外国語の獲得・処理・学習に関する心理言語学研究の成果をご紹介しながら,心的プロセスの解明がどのような授業改善のヒントをもたらしてくれるか,外国語教育への心理言語学的アプローチのオモシロさとムズカシさなどについてお話ししたいと思います。
● JR尼崎駅(北口)より東側遊歩道を北側へ回り込み,キューズモール東側から北側へ折れる。西へ直進し,会場校3階の入り口から,階段またはエレベータで5階受付へ。注:キューズモールは10時開店のため,朝は通りぬけできません。
学内には駐車スペースがありませんので,公共交通機関をご利用ください。
以下、発表者の皆さまに各発表形式別に簡単な注意事項を記します。(発表の形式や様子についてはこちらを参照して下さい)
発表時間:卒論 25分(15分 質疑応答 10分)、修論 30分(20分 質疑応答 10分)
パソコン:各教室にはプロジェクター(及びPC接続用のVGAケーブル)は設置されていますが,PC/Macは各自ご持参下さい。Macの場合,VGAアダプタが必要 となりますので,そちらもご持参下さい。PC/Macをお持ちでない方は,事前にセミナー担当者に問い合わせて下さい。
AV機器:CDやDVDの使用は可能です。MDやカセットは不可。
会場下見:発表会場の下見、パワーポイントスライドのテスト等は、午前の部の方は、開会行事後から第1発表の間までの時間に、午後の部の方は、昼食休憩の間に、各自で行ってください。
発表資料:予稿集・プレゼンテーションスライド(任意) 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
コアタイム: 11:25 ~12:20の間は,必ず各自の持ち場に待機して下さい。その間,11:25〜11:40,11:45〜12:00,12:05〜12:20,の各回15分のセッションにて,参会者に説明や質疑を行って下さい。
ポスター:【サイズ】最大A0までにて作成。(一枚ものでも,A4を組み合わせても可)【貼付け】ボードまたは壁に貼付け。貼付けに必要な資材は,学会事務局で準備します。【掲示時間】9:30~13:20
パソコン: PC/Macは各自ご持参下さい。
AV機器: PCから音声を出す場合,ポータブルスピーカー等は各自ご持参下さい。その他,CDやDVD等のご使用については,学会事務局にお問い合わせ下さい。
什器: 長机やイスは発表スタイルに応じて準備しますので,学会事務局にお尋ね下さい。発表資料:予稿集・ポスター 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
プログラム(PDF)をダウンロードいただけます。以下の表紙をクリックして下さい(別ウィンドウ)
2017年02月04日公開
発表要旨(PDF)をダウンロードいただけます
2017年2月公開予定
第20回卒論・修論研究発表セミナー発表要旨(PDF)
プログラムや発表要旨に変更や修正が生じた場合、改訂版を公開いたしますので、定期的にご確認をお願い致します。
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
TEL: 078-803-7684 [dial-in]
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
12:30 開会 コーディネーター: 泉 惠美子 先生(京都教育大学)
12:40-13:50 講演 「小中の英語教育で求められるもの:次期学習指導要領を踏まえて」 講師 酒井 英樹 先生(信州大学)
13:50-14:00 休憩
14:00-15:00 セミナー① 「小学校外国語活動におけるチャンツの効果と指導法」 講師 真崎 克彦 先生(関西大学非常勤,元兵庫教育大学附属小学校)
15:00-15:20 休憩
15:20-16:20 セミナー②「英語教育におけるCAN-DO評価とパフォーマンス評価」 講師 泉 惠美子 先生(京都教育大学)
KELES 第40回セミナーご案内 (PDF)
下記のフォームをご利用ください(12月21日より受付開始)
第40回KELESセミナー(全国英語教育学会平成28年度第3回英語教育セミナー)参加登録/キャンセル フォーム(新しいタブ・ウィンドウで開きます)
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
日時:2017(平成29)年2月12日(日)9:30~17:30
会場:関西国際大学 尼崎キャンパス → アクセス
〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
内容:学部学生による卒業論文・大学院生による修士論文の研究発表(口頭発表またはポスター発表)
コメンテーター:主催・共催学会に所属する教員・研究者
プログラムはこちら(2月3日公開)。
関西英語教育学会では、大学英語教育学会(JACET)関西支部,外国語教育メディア学会(LET)関西支部との共催で,本年度も下記の要領で「卒論・修論研究発表セミナー」を開催致します。お忙しい時期とは存じますが、多くのご発表ならびにご参加を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
講師:横川博一(神戸大学 教授)
演題:外国語運用能力はいかに熟達化するか―言語情報処理の自動化プロセスを探る
概要:今,日本の英語教育は抜本的改革を迫られているように思います。英語教育を取り巻く動きには枚挙にいとまがありません。教育のパラダイム転換の動きと相まって声高に英語教育改革が叫ばれる背景にあるのは、英語運用能力の育成と向上に対する強い期待と要請と言ってよいでしょう。
英語運用能力の育成には、運用能力の基盤となる知識の形成と運用スキルの習熟を図ることが必要であり、言語処理の自動化が英語運用能力の熟達化にとって重要な役割を果たします。しかし、その認知メカニズムは十分に明らかにされているとは言い難く、その認知メカニズムを解明することが、英語運用能力育成のカギともなります。
このトークでは、これまでのおよそ30年を振り返って、英語教育・心理言語学との出会いから、私自身の失敗と試行錯誤の連続としての授業実践も踏まえ、最近の科研プロジェクトで取り組んできた外国語の獲得・処理・学習に関する心理言語学研究の成果をご紹介しながら、心的プロセスの解明がどのような授業改善のヒントをもたらしてくれるか、外国語教育への心理言語学的アプローチのオモシロさとムズカシさなどについてお話ししたいと思います。
参加費:会員、非会員とも 500円(当日、予稿集を配布)
プログラム内に,アフタヌーンティーを設定する予定です。発表者・コメンテーターや講師の先生方,参会者の皆さまとの気軽な交流の時間です。
上記の内容につきまして、変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
発表資格:学部生・院生(発表者は学会員である必要はありません)
申込期間:2016年12月16日(金)〜2017年1月20日(金)まで【厳守】
発表分野:外国語教育,外国文学,言語学および関連分野
発表形式:口頭発表またはポスター・デモ発表(発表申込時に発表形式の希望をお尋ねしますが,発表者数によっては,口頭↔ポスター・デモ発表に変わっていただくこともございます)(発表形式についての詳細は,前回の様子をご覧下さい こちら)
発表時間:
<口頭発表>卒業論文25分(発表15分,コメント・質疑応答10分)・修士論文30分(発表20分,コメント・質疑応答10分)
<ポスター・デモ発表>卒業論文・修士論文とも掲示・質疑(コアタイム45分:15分×3セット)
使用言語:日本語または英語
予稿集:発表者の方には,2017年1月27日(金)までに,予稿集原稿(A4用紙2ページ以内)をご提出いただきますのであらかじめご承知おき下さい。発表者の方にはテンプレートをお送りします。
発表申込方法:第20回卒修論セミナーホームページ【申込フォーム】より,必要事項(発表言語での論文タイトル・キーワード(3~5語)・日本語200字程度, 英語400 words程度の発表要旨を含む)を入力・送信してください。
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「文法の練習を授業でどのように行うか」
松下 信之 先生(大阪府教育センター)
14:40-16:00 「英語の文法指導・学習について-本講演者のこれまでの研究成果から言えそうなこと-」
白畑 知彦 先生(静岡大学・教授)
16:00-16:20 フロアとのQ & A セッション
16:20-16:30 閉会のことば
 【プロフィール】
【プロフィール】
大阪府教育センター指導主事。大阪府立勝山高等学校、大阪府立高津高等学校を経て現職。2014年度パーマー賞受賞。書籍の分担執筆等:検定教科書「ELEMENT English Communication Ⅰ~Ⅲ」(啓林館)、「英語で英語を読む授業」(研究社)、「英語で教える英文法」(研究社)、「英語授業ハンドブック・高校編」(大修館)など。
これまで文法指導というと、形式についての明示的な説明と問題演習が中心に行われ、生徒がその文法を実際のコミュニケーションで使用する機会が十分に設けられていない、という批判を受けることが多くありました。ただ、実際の授業で学んだ文法を使う活動を設定しても、生徒からアウトプットを引き出すことが難しい、という声をよく聞きます。今回は、生徒の意識を文法の使用に向け、生徒が学んだ文法を使用できるようになるための橋渡しの役割をする「練習」や生徒のアウトプットを引き出す工夫について、具体例を用いて紹介します。
 【プロフィール】
【プロフィール】
1957年6月10日,静岡県森町生まれ。専門は言語習得,外国語(英語)教育学。早稲田大学第一文学部,青山学院大学大学院,アリゾナ大学大学院修了,博士(文学)大阪大学。現在,静岡大学教育学部教授,並びに愛知教育大学・静岡大学大学院教育学研究科(博士課程)協同教科開発学専攻教授。主な書著に『改訂版 英語教育用語辞典』(共著,大修館書店),『英語習得の「常識」「非常識」』(編著,大修館書店),『詳説 第二言語習得研究』(共著,研究者),『ことばの習得』(共著,くろしお出版),『日本の英語教育の今,そして,これから』(分担執筆,開拓社)がある。(本プロフィールは,『英語指導における効果的な誤り訂正—第二言語習得研究の見地から』の著者紹介を拝借いたしました)
外国語(または第二言語)の習得、学習の仕方は千差万別だと思います。つまり、何歳の学習者が、どこで、どのような形態で学習するかによっても、その効率よい学習方法は異なってくると思います。そして、それぞれの異なる場合で、教え方へのアドバイスも異なってきます。今回の講演では、「日本の学校という学習環境で、ごく普通の(小学生)、中学生、高校生、(大学生)が、教師が教科書を使用し、英語を外国語として学習する場合」という学習条件(日本では最も一般的な環境)での、本講演者が「効果的(かもしれない)」と考える「英文法の指導(今セミナーのテーマ)」を中心にお話ししたいと考えています。
上記の学習条件では、耳や目から入って来る言語習得に必要なインプットが、「言語をかなり自然に習得できる条件」からはあまりにもかけ離れています(そもそも、豊富な言語インプットを受けていそうな母語獲得の時でさえも、「刺激の貧困」ということが言われているのですから)。しかしながら、有利な点は、学習者は一般的な認知レベルが高くなってきていて、母語を獲得している人達だということです。このような状況にいる学習者には、「文法の規則を説明して教えてあげる」ことは有効な方法だと思います。ただし、このような明示的な文法指導も決して「完全無欠な」方法ではないことも、本講演の中でお話しして行きたいと思います。
白畑先生のセミナースライド ダウンロードはこちら(pdf)
KELES 第39回セミナーご案内 (PDF)
下記のフォームをご利用ください(11月25日より受付開始 12月23日17時半,教室定員に達したため,申込を締め切ります。多数の参加申し込み,ありがとうございました。)
第39回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「『超』若手中・高教師としての研究への向き合い方」
山形 悟史 先生(関西大学第一高等学校・教諭)
14:40-16:00 「はじめの一歩を踏み出すために:英語教育研究の入口」
浦野 研 先生(北海学園大学・教授)
16:00-16:20 フロアとのQ & A セッション
16:20-16:30 閉会のことば
 【プロフィール】
【プロフィール】
関西学院大学卒業(人間福祉学)。大阪教育大学大学院修了(英語科教育学)。大学院修了後,公立中学校教諭として1年間の勤務を経て,現職。応用言語学でこれまで得られた研究知見が,実際に日本の中学校・高等学校での授業実践に応用できるのか,そうであればどのように授業に落とし込むべきか,日々「楽しく」仕事をしています。特に,基本動詞やコロケーションを教室環境で学習する効果的な方法や,またそれらがどのような意味表象を形成しているのか,心理実験的手法を用いた研究にも興味があります。
大学院を修了して約1年,教育・研究のどちらを取ってもまだまだ駆け出しの身ではありますが,なんとかそれらを両立させようともがいております。当日は,日ごろの授業の紹介を交えながら,個人的な教育・研究活動の両立方法についてお話をさせて戴きます。私自身,当日参加される皆様からのご意見を存分に吸収して,成長をしたいと思っております。なお,発表は以下の流れに沿って進行の予定です。
(1) 研究を始めたきっかけ
(2) 研究について
・テーマの設定(日々の仕事の中で,研究課題を立てる工夫など)
・データ収集,分析(研究デザインの組み方と戦略)
・論文投稿に至るまで,投稿からのプロセスなど(修士論文完成から国際誌採択まで)
・研究内容(Language Teaching Research 掲載論文をもとに)
(3) 教育と研究の両立
・教育をしながら研究してゆくための工夫,メリット,むずかしさなど(最近の取り組みを踏まえて)
 【プロフィール】
【プロフィール】
北海学園大学経営学部教授,名古屋学院大学大学院外国語学研究科客員教授。ハワイ大学大学院修士課程修了(第二言語としての英語研究),同博士課程中退(第二言語習得)。主な研究対象は第二言語習得と英語教育で,前者では特に統語と形態素の習得に関心があり,後者では特定目的のための英語(ESP)教育やタスク・ベースの言語指導(TBLT)を中心に研究と教育実践を行っています。
英語教育研究には様々な立場の方が関わっているため,「研究」ということばからイメージする内容は人それぞれ異なるかもしれません。そこで今回のセミナーでは,特に研究の入口に焦点を当てて,研究と研究でないものの違い,「よい」研究の条件,研究と実践の関係,研究成果の実践への応用可否といった考えについて整理しながら,研究課題の設定方法や研究手法の選択方法についての理解を目指します。
下記のフォームをご利用ください(8月31日より受付開始)
第38回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
- 会場内に「託児コーナー」が設置されます。ご希望の方は公式サイトより申込下さい。
- 学生会員の交流の場の提供として,「第4回大学生・大学院生フォーラム」が開催されます。
- 「学生会員の研究大会参加助成制度」が設置されました。詳しくは,こちらをご覧ください。
2016年度関西英語教育学会(第21回)研究大会を下記の要領で開催致します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
→ プログラムのダウンロード
→ アブストラクトのダウンロード
2016 (平成 28) 年
6 月 11日(土)12:10~17:45(12:00受付開始)
6 月 12日(日)10:00~16:25(9:30受付開始)
大阪教育大学天王寺キャンパス
〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町4-88 → アクセス
*駐車場スペースはございませんので,公共交通機関または近隣の駐車場をご利用下さい。
関西英語教育学会会員:無料
非会員 (一般):2,000 円
非会員 (学部学生・大学院生):1,000 円
*学生証をご提示下さい。提示がない場合は一般参加費となります。
*事前申込の必要はございません。当日会場にお越し下さい。
*上記参加費で2日間ご参加いただけます。会場では名札をご使用下さい。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
中学英語教科書のアクティビティーを考えるー教科書の役割,教師の役割ー
奥住 桂 (埼玉県宮代町立前原中学校)
音読のバリエーションに応じた音声編集
菅井 康祐 (近畿大学)
(注意)こちらのWSは音声編集ソフトAudacityがインストールされたコンピュータ,イヤホン/ヘッドホンを持参の上ご参加下さい。音声編集ソフト Audacityのダウンロードはこちら WSにて使用する音声ファイルはこちら
教師生活40年を振り返る
村田純一(神戸市外国語大学)
汎用的教材研究術
山岡 大基(広島大学附属中・高等学校)
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
○第1日目にご参加された方は,名札を付けて入場下さい。
○会場周辺には飲食店があまりございません。各自昼食をご持参下さいますようよろしくお願いいたします。
英語授業におけるペアワーク:What’s going on between the learners?
吉田 達弘 (兵庫教育大学)
坂本 南美 (兵庫県立大学附属中学校)
廣畑 陽子 (龍野北高等学校)
上山 尚穂子(西宮今津高等学校)
生徒の英語力の向上を妨げる指導 vs. 生徒の英語力の向上を促進する指導
鈴木 寿一 (京都外国語大学)
脳機能画像解析法と英語教育研究:fMRIでできること
大嶋 秀樹 (滋賀大学)
① 13:00~13:30 ② 13:35~14:05 ③ 14:10~14:40 ④ 14:45~15:15
[第1室 第4講義室]
① 事例報告:パスポートを使った中高大一貫英語教育の実践/山岡 賢三(樟蔭学園英語教育センター)
② 事例報告:小中連携の英語教育に向けて-小中連携の成果と課題(学校現場での視点より)-/高木 浩志(宝塚市立逆瀬台小学校)
③ 研究発表:英語と日本語の音の違いに気づかせる小学生への指導の試みー「相手に伝わる発音」への効果ー/山本 玲子(京都外国語大学)・里井 久輝(龍谷大学)
④ 研究発表:小学校教員をめざす学生の認知的道具の理解を促す外国語活動指導法の開発/脇本 聡美(神戸常盤大学)
[第2室 第2会議室]
① 研究発表:英語による導入の効果測定−習熟度と動機づけの観点から−/井上 聡(環太平洋大学)
② 研究発表:学生のプレゼンテーション力は、評価者としての学生の評価力に影響を及ぼすか?ー教員による評価と学生による評価との関係からー/笠巻 知子(立命館大学)
③ 事例報告:学習者に「考えて」英語で「発信」する力をつけるための授業実践/齋藤 由紀(大阪国際大学)・佐々木 緑(大和大学)
④ 事例報告:中学2年生が挑戦した英語ディベート〜授業デザインと教師の支援〜/関田 信生(東海大学付属仰星高等学校中等部)
[第3室 第8講義室]
① 研究発表:英語の授業において「英語の授業」は唯一の現実か?—メタ・コミュニケーションの視点からの一考察—/榎本 剛士(金沢大学)
② 研究発表:プロジェクト発信型英語プログラムにおける英語コミュニケーションテストOPIc利用の試み/大賀 まゆみ(立命館大学)・生駒 万貴(立命館大学)
③ 事例報告:復習としてのテスト効果の検証ー高校生の語彙学習を対象としたケーススタディ/南 侑樹(大阪府立槻の木高等学校)
④ 研究発表:論理性を高めるライティング活動の検討 —論理性の上昇に寄与する要因を探る—/増見 敦(神戸大学附属中等教育学校)
[第4室 第9講義室]
① 研究発表:多読で伸びる文法力/高瀬 敦子(関西学院大学)・吉澤 清美(関西大学)・大槻きょう子(奈良県立大学)
② 事例報告:プロジェクト発信型英語プログラムへの6W1Hメソッドの導入/辻 香代(立命館大学)
③ 研究発表:仮定法用語一貫性理論:仮定法に係わる用語に論理的一貫性を具備させる/秦 正哲(兵庫医療大学)
[第1室 第5講義室]
① 事例報告:New E-book: Integrated-reading iPad textbook/夫 明美(大阪女学院大学・短期大学)・Paul Lyddon(大阪女学院大学・短期大学)
② 研究発表:英語リスニング力とスピーキング時における不安の関連性について/中西 悠子
清水 裕子 (立命館大学,関西英語教育学会副会長)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2016年度(第21回) 研究大会 プログラム(PDF)
5月2日公開(6日最新版)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2016年度(第21回)研究大会 研究発表・公募フォーラム・アブストラクト(PDF)
関西英語教育学会2016年度(第21回)研究大会 講演・セミナー・ワークショップ等アブストラクト(PDF)(5月6日 最新版)
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
今般,お手元に届きました配送物につきまして,誤って封入されたものがございますので,ご確認いただき,そちらについては関係する方以外は無視していただきますようお願いいたします。
2015年度の会費をお支払いの会員の皆さまのお手元には,以下の書類や印刷物が入っていたと思います。
1)ニューズレター
2)学会費納入のお願い
3)研究大会CFP(2次)
4)2016年度会費納入済みのお知らせ
5)振込用紙
6)紀要SELT
7)KELESジャーナル
上記の赤でボールドの 4)につきましては,本来ごく少数が該当する方(2016年度会費を既に納入いただいた方)にのみ封入するべきものでした(17人)。しかしながら,多くの方々に誤って封入されていることが確認されました。
つきましては,2016年3月末時点において今年度(2016年度)の年会費をお支払いでな方々については,*4)の書類は無視していただき,2016年度の会費をお支払いくださいますようよろしくお願いいたします。万一,確認を要する場合には,事務局までお問合せいただければ幸いでございます。
2016年度関西英語教育学会(第21回)研究大会を下記の要領で開催致します。
今回も昨年度同様,研究大会が2日間に渡って開催され,研究発表・事例報告に加えて,公募ワークショップ・公募フォーラムの発表募集を行います。奮ってご応募下さい。多くの皆様のご発表・ご参加をお待ちしております。
日程
2016(平成 28) 年 6 月 11日(土)・12 日 (日)
大阪教育大学天王寺キャンパス アクセス
関西英語教育学会会員:無 料
非会員(一般):2,000 円
非会員(学部学生・大学院生):1,000 円 (※学生証を提示して下さい)
1日目:6月11日(土)
2日目:6月12日(日)
発表者は、関西英語教育学会の会員にかぎります。
※ 2016 年 4 月 20 日(水)までに,会員の方は 2016 年度の学会費を納入していることが必要です。非会員の方は、会員手続き(入会申込および会費納入)を済ませて下さい。入会手続きおよび会費納入が確認されない場合は、発表自体が取り消しとなりますのでご注意下さい。
※ 共同研究者は学会員であることが望ましいですが、必ずしも会員である必要はありません。ただし、当日の発表は学会員が行って下さい。
広く英語教育にかかわる理論的・実証的研究および授業実践に関する報告で、未発表のものに限ります。
日本語または英語
(1)研究発表 (理論的、実証的研究の発表)
(2)事例報告 (授業実践に関する報告)
(3)ポスター・デモ発表(ポスター発表・対面発表・教材教具などのデモなど)
(4)公募ワークショップ(1人または複数の講師による英語授業実践をテーマとした企画)
(5)公募フォーラム(コーディネータおよび数名の英語教育にかかわる理論的・実証的研究をテーマとした企画)
(1)口頭発表(1 件につき発表 20 分、質疑応答 5 分〜10分* プログラム構成によって質疑の時間の若干の変動あり)
(2)ポスター・デモ発表(発表コアタイム 60 分)
(3)公募ワークショップ・公募フォーラムは1件あたり90分です。
本ページの申込フォームから、必要情報(以下の内容)を入力して送信して下さい。
2016 年 2 月 11 日(木) ~ 4 月 20 日(水) 23:59 まで
※期限厳守。期限を過ぎたものはいかなる理由があっても受け付けることができませんので,留意して下さい。
2016 年 4 月 25 日(月) までに登録されているメールアドレス宛てに、電子メールにて通知します。
※4 月26日(火) を過ぎても通知がない場合は、学会事務局(下記参照)まで電子メールにてお問い合わせ下さい。
研究発表・事例報告・ポスター・デモ発表・公募フォーラム・公募ワークショップは,大会2日目に予定されていますが,応募数によっては,大会1日目に開催することもあります。なお,日程や時間帯の指定はご遠慮下さい。
※ 発表資格など発表応募要領をよくご確認ください。
※ 発表の内容が未発表のものであることを確認して下さい。
※ 入力内容に誤りがございますと申込手続きを進めることができませんので、ご注意ください。
※ 「申込フォーム」での送信後、登録完了のお知らせを折り返しお送りいたしますのでご確認ください。
※ ご登録いただいた個人情報は厳重に管理を行い、研究大会発表申込の手続き以外には使用いたしません。
ご自由にダウンロード・印刷・掲示ください
関西英語教育学会 2016年度(第21回) 研究大会 プログラ厶
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
平成27年度学会費納入のお願い
今年度(平成27年度)の学会費の納入がまだの方がいらっしゃるようです。該当の方は,2月末日までの納入をよろしくお願い致します。
特に,2016年8月20日(土)・21日(日)に埼玉にて開催される,第42回全国英語教育学会埼玉研究大会にて,発表を予定なさっている方々は,今年度分の会費の2月末までの納入が発表資格の条件になりますので,十分にお気をつけ下さいませ。
学会費納入に際しては,以下のページをご参照下さい。
http://www.keles.jp/join/
主催:関西英語教育学会(KELES)
共催:大学英語教育学会(JACET)関西支部、外国語教育メディア学会(LET)関西支部
「第19回卒論・修論研究発表セミナー プログラム」について変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
日時:2016年2月11日(木・祝)
場所:関西国際大学 | 尼崎キャンパス | info 〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
参加費:会員、非会員とも 500円
※事前申込不要 当日,予稿集を配布 直接会場にお越しください
発表者の皆さまは必ずこちらをご覧ください
プログラム(PDF)のダウンロードはこちらからどうぞ(02月04日更新)
New! スペシャル・トークの資料をアップロードしましたこちらからどうぞ(02月13日更新)
9:00 - 受付(関西国際大学・尼崎キャンパス・5階受付にお越しください) info
9:20 – 9:30 開会行事(501中講義室)
司会: 鳴海 智之(兵庫教育大学)
開会の挨拶: 村田 純一(関西英語教育学会会長・神戸市外国語大学)
9:40 – 11:20 午前の部 info
11:25 – 12:20 ポスター・デモ発表コアタイム info
12:20 – 13:20 昼食休憩
13:20 – 15:35 午後の部 info
15:40 – 17:00 スペシャル・トーク(501中講義室) info
「英語教育改革と技術移転の問題点」
講師: 沖原 勝昭 先生(京都ノートルダム女子大学・教授)
講師紹介: 大嶋 秀樹(滋賀大学)
17:05 – 17:15 閉会行事(501中講義室)
閉会の挨拶: 大和 知史(関西英語教育学会幹事長・神戸大学)
17:30 – 19:00 レセプション
会費:一般2500円,学生1000円(当日受付にてお支払い下さい),発表者は無料
会場:関西国際大学・尼崎キャンパス2階食堂
どなたでもご参加いただけます。どうぞお気軽にご参加下さい!!
①9:40~10:10 ②10:15~10:45 ③10:50~11:20
コメンテーター:中野 陽子(関西学院大学)・谷村 緑(京都外国語大学)
① B: 三種類のコーパス比較 /中西 淳(甲南大学)
② M: 黙読における、語彙重複を介さないプライミング効果が、前置詞句処理の自動化に及ぼす影響/藤田 宏樹(大阪教育大学)
③ M: BE動詞の分析:認知言語学の視点より/蛭子 明日香(京都教育大学)
① B: 小学校外国語学習におけるドラマ教育の可能性 —インプロが外国語活動に与える効果を探る—/米永 晶子(京都教育大学)
② M: カズオ・イシグロの作品における理想と現実/山田 純貴(京都教育大学)
③ M: The Effectiveness of Using Songs in English Classes in Japan/大浦 詩織
(大阪教育大学)
コメンテーター:中田 賀之(同志社大学)・田中 博晃(近畿大学)
① B: 小学校における国際交流の効果—国際的志向性に注目して—/足立 亜希保
(京都教育大学)
② B: A Study on Peer-Writing Activity Based on Self-Determination Theory/山本 大輔(京都教育大学)
③ M: ダイナミック・アセスメントとCan-do評価を用いた学習者自律の育成/二宮 宏樹(京都教育大学)
コアタイム 11:25~12:20(S1: 11:25〜11:40, S2: 11:45〜12:00, S3: 12:05〜12:20)
① B: よりよいティーチングを求めて〜教室談話を変える私の試み〜/緒方 健人(神戸市外国語大学)
② B: Input型からOutput型へのコミュニケーション能力向上の指導法:To不定詞における指導/北山 敦士(関西国際大学)
③ M: ペアでの英語ライティングにおける高校生の主体的学びの研究/上山 尚穂子(兵庫教育大学)
【ポスター第2室】(505演習室)
① B: Speaking Influence on the Self-esteem of the Students in Global Studies/長野 惇(関西国際大学)
② B: 母の死を契機とする私の家族観—娘、姉、未来の母親の視点から/俵積田 香菜(神戸市外国語大学)
③ M: 大学の英語の授業における学習者の主体性に関する研究 /岡 久美子(兵庫教育大学)
④ M: 内容言語統合学習(CLIL)の高等英語教育機関における応用可能性/谷野 圭亮(大阪教育大学)
① B: フォニックス絵本の開発/小嶋 亜依(神戸市外国語大学)
② M: 外国語活動における児童の相互行為能力の発達に関する研究 /入江 由美子(兵庫教育大学)
③ M: 英語教育における反転型授業の活用:音読・インプットを重視した中等教育向け授業モデルの提案/谷口 舜(大阪教育大学)
④ M: 第二言語の理解における外国語訛りの影響: 文理解のレベルにおける処理困難性について/竹山 智子(大阪教育大学)
④13:20~13:55 ⑤13:55~14:25 ⑥14:30~15:00 ⑦15:05〜15:35
コメンテーター: 佐久 正秀(大阪信愛女学院短期大学)・平井 愛(神戸学院大学)
④ B:日本の大学生の英語スピーキング能力と学習経験の関係について/南部 久貴(滋賀大学)
⑤ M: ICTを用いた英語スピーキング能力の強化 −字幕欠落を含むビデオを用いて生徒の語彙と動機づけ向上を目指して−/堀本 孝正(大阪教育大学)
⑥ M: Developing L2 Speaking Fluency and Accuracy in EFL Undergraduate Students Based on Flipped Instruction Methodology/西村 真成(大阪教育大学)
コメンテーター:加賀田 哲也(大阪教育大学)・名部井 敏代(関西大学)
④ B: コミュニケーションへの積極的な態度を育むためのタスクの可能性/宮本 杏子(京都教育大学)
⑤ B: 教師の介入による学生のコミュケーションの豊かさに関する質的事例研究/安村 唯(京都教育大学)
⑥ B: 英語ライティングにおける自己表現活動の意義/立入 靖規(京都教育大学)
⑦ M: 協働学習を取り入れた、中学校におけるリーディング活動/津田 優子(京都教育大学)
コメンテーター: 玉井 健(神戸市外国語大学)・吉田 達弘(兵庫教育大学)
④ B: FonFと教師の役割/濱地 亮太(関西大学)
⑤ B: バフチンの対話原理の能動的応答に関する研究ー小学校英語教育における実践/臼井 理紗(京都教育大学)
⑥ M: 学習困難を抱える学習者に対する多感覚学習法を用いた読み書きの指導/阪上 瑞穂
(大阪教育大学)
⑦ M: 生徒の自尊心を高めることに焦点を置いた授業実践/西川 美咲(大阪教育大学)
講師:沖原 勝昭 先生 (京都ノートルダム女子大学・教授)
演題:英語教育改革と技術移転の問題(Technology Transferred for ELT Innovations, Promising?)
現在,英語教育には改革・刷新が求められている,と言われます。このことはわが国にとどまらず,世界の多くの国においても同様です。また,現在だけでな く,これまでも常に英語授業の改善が叫ばれてきました。このような要請が出される背景には,学校の教科の中で,外国語(英語)は「期待値」と「実態値」の 乖離が最も大きな科目であるという事情も影響しているでしょう。そして,英語教育の改革が叫ばれるたびに,新機軸,すなわち,新しい技術が導入され,新し い授業実践が求められてきました。このような状況を目の当たりにして,本学会の村田純一会長は,KELES Newsletter(2015年 第1号)の巻頭言「大転換をすべきこと」において,「政治の側から無理難題を突きつけられるのではまともに聞いていられません。」と嘆いておられます。私 も同様の受け止め方をしており,英語教育改革はこのまま進んでよいのか,危惧しています。
このたびのスペシャル・トークでは,英語教育を改革・改善するために移転されてきた新技術はその目的に合致したものかどうか,を検証してみたいと思いま す。つまり,新技術が創案された「起点コンテクスト」と日本の「移転先コンテクスト」との適合性ということです。これら2つのコンテクストがミスマッチの 関係であれば,新技術は効力を発揮できず,英語教育の改善は成功しません。検証の対象となる導入技術として,戦後間もなく移転されたOral Approach, 1970〜1980年代のCommunicative Language Teaching, および最近のContent and Language Integrated Learning (CLIL)を取り上げます。
スペシャル・トーク 講演資料pdf(281kb)
● JR尼崎駅(北口)より東側遊歩道を北側へ回り込み,キューズモール東側から北側へ折れる。西へ直進し,会場校3階の入り口から,階段またはエレベータで5階受付へ。注:キューズモールは10時開店のため,朝は通りぬけできません。
学内には駐車スペースがありませんので,公共交通機関をご利用ください。
以下、発表者の皆さまに各発表形式別に簡単な注意事項を記します。(発表の形式や様子についてはこちらを参照して下さい)
発表時間:卒論 25分(15分 質疑応答 10分)、修論 30分(20分 質疑応答 10分)
パソコン:各教室にはプロジェクター(及びPC接続用のVGAケーブル)は設置されていますが,PC/Macは各自ご持参下さい。Macの場合,VGAアダプタが必要 となりますので,そちらもご持参下さい。PC/Macをお持ちでない方は,事前にセミナー担当者に問い合わせて下さい。
AV機器:CDやDVDの使用は可能です。MDやカセットは不可。
会場下見:発表会場の下見、パワーポイントスライドのテスト等は、午前の部の方は、開会行事後から第1発表の間までの時間に、午後の部の方は、昼食休憩の間に、各自で行ってください。
発表資料:予稿集・プレゼンテーションスライド(任意) 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
コアタイム: 11:25 ~12:20の間は,必ず各自の持ち場に待機して下さい。その間,11:25〜11:40,11:45〜12:00,12:05〜12:20,の各回15分のセッションにて,参会者に説明や質疑を行って下さい。
ポスター:【サイズ】最大A0までにて作成。(一枚ものでも,A4を組み合わせても可)【貼付け】ボードまたは壁に貼付け。貼付けに必要な資材は,学会事務局で準備します。【掲示時間】9:30~15:40
パソコン: PC/Macは各自ご持参下さい。
AV機器: PCから音声を出す場合,ポータブルスピーカー等は各自ご持参下さい。その他,CDやDVD等のご使用については,学会事務局にお問い合わせ下さい。
什器: 長机やイスは発表スタイルに応じて準備しますので,学会事務局にお尋ね下さい。発表資料:予稿集・ポスター 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
プログラム(PDF)がダウンロードいただけます。以下の表紙をクリックして下さい(別ウィンドウ)
2016年02月04日公開
発表要旨(PDF)がダウンロードいただけます
2016年2月公開予定
第19回卒論・修論研究発表セミナー発表要旨(PDF)
プログラムや発表要旨に変更や修正が生じた場合、改訂版を公開いたしますので、定期的にご確認をお願い致します。
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
TEL: 078-803-7684 [dial-in]
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
関西英語教育学会卒論・修論研究発表セミナーでは、以下の2つの発表形式のうちのいずれかで発表していただきます。2つ目の形式は,従来のポスター発表だけでなく,教材やソフトなどをデモンストレーションできるような形式で,よりオーディエンスとの密なコミュニケーションを見込むことができます。是非チャレンジしてみて下さい。
◎口頭発表
・5~6部屋に分かれて、1人ずつ発表します。
・発表時間は1発表につき卒論15分、修論20分です。
・各発表後、コメンテーターからのコメントと、フロアとの質疑応答のための時間が10分あります。
・各教室にはプロジェクターとVGAケーブルが設置されていますので、Powerpoint・Keynoteが使えます。
・PC/Macは各自ご持参下さい。Macの場合、VGAアダプタもご持参下さい。
・PC/Mac をお持ちでない方は,事前にセミナー担当者に問い合わせて下さい。
<過去の口頭発表の様子>
◎ポスター・デモ発表New!
・今回からの新形式です。これまでのポスター発表に加え,スライドを提示しての対面発表形式,教材やソフトなどを示しながら発表するデモンストレーション形式などを含めることになりました。
・発表者全員が、1つ(あるいは複数)の部屋にポスターを掲示・机などに教材等を配置します。
・1時間のコアタイムを15分×3回で区切ります。その時間内は目の前の参会者に向けて説明や質疑を行って下さい。コアタイムの間は担当の場所に待機していただきます。
・ポスターは最大A0サイズ(841mm x 1189mm)までです。
<A0ポスターの例>
・→の写真と同様のテンプレートは以下の画像をクリックしてダウンロードして下さい。
・A4用紙にPowerpointなどで発表内容をまとめたものを組み合わせて掲示することも可能です(その場合,A4用紙16枚分に相当します)。
<A4ポスターの例>
・掲示に必要な資材(ボード・押しピン等)は、学会で準備します。
<対面発表の例>
・対面発表は,コンピュータやタブレットなどで,スライドや画面を提示したり,準備した資料などを提示しながら,参会者と対話するように発表をする形式です。
・教材や教案の作成をもって卒業・修士論文などになっている場合,最適な方法ではないでしょうか。
・掲示に必要な長机は、学会で準備します。
・このように,スライドやデータテーブルなどを画面で見せながら話をすることができます。
・自作のソフトなどの動作させたり,音声・映像教材などを提示する方にお勧めの方法です。
<過去のポスター発表の様子>
日時:2016(平成27)年2月11日(木・祝)9:30~17:30
会場:関西国際大学 尼崎キャンパス → アクセス
〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
内容:学部学生による卒業論文・大学院生による修士論文の研究発表(口頭発表またはポスター発表)
コメンテーター:主催・共催学会に所属する教員・研究者
プログラムはこちらをご覧下さい(2月4日公開)
関西英語教育学会では、大学英語教育学会(JACET)関西支部,外国語教育メディア学会(LET)関西支部との共催で,本年度も下記の要領で「卒論・修論研究発表セミナー」を開催致します。お忙しい時期とは存じますが、多くのご発表ならびにご参加を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
講師:沖原勝昭(京都ノートルダム女子大学 教授)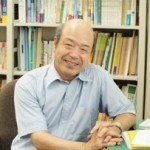
演題:英語教育改革と技術移転の問題点(Technology Transferred for ELT Innovations, Promising?)
概要:現在,英語教育には改革・刷新が求められている,と言われます。このことはわが国にとどまらず,世界の多くの国においても同様です。また,現在だけでなく,これまでも常に英語授業の改善が叫ばれてきました。このような要請が出される背景には,学校の教科の中で,外国語(英語)は「期待値」と「実態値」の乖離が最も大きな科目であるという事情も影響しているでしょう。そして,英語教育の改革が叫ばれるたびに,新機軸,すなわち,新しい技術が導入され,新しい授業実践が求められてきました。このような状況を目の当たりにして,本学会の村田純一会長は,KELES Newsletter(2015年 第1号)の巻頭言「大転換をすべきこと」において,「政治の側から無理難題を突きつけられるのではまともに聞いていられません。」と嘆いておられます。私も同様の受け止め方をしており,英語教育改革はこのまま進んでよいのか,危惧しています。
このたびのスペシャル・トークでは,英語教育を改革・改善するために移転されてきた新技術はその目的に合致したものかどうか,を検証してみたいと思います。つまり,新技術が創案された「起点コンテクスト」と日本の「移転先コンテクスト」との適合性ということです。これら2つのコンテクストがミスマッチの関係であれば,新技術は効力を発揮できず,英語教育の改善は成功しません。検証の対象となる導入技術として,戦後間もなく移転されたOral Approach, 1970〜1980年代のCommunicative Language Teaching, および最近のContent and Language Integrated Learning (CLIL)を取り上げます。
参加費:会員、非会員とも 500円(当日、予稿集を配布)
セミナー終了後,懇親会を開催しますので,奮ってご参加下さい。
一般 2,500 円 学生・院生 1,000 円
上記の内容につきまして、変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
発表資格:学部生・院生(発表者は学会員である必要はありません)
申込期間:2015年12月19日(土)〜2016年1月22日(金)まで【厳守】
発表分野:外国語教育,外国文学,言語学および関連分野
発表形式:口頭発表またはポスター・デモ発表(発表申込時に発表形式の希望をお尋ねしますが,発表者数によっては,口頭↔ポスター・デモ発表に変わっていただくこともございます)(発表形式についての詳細はこちら)
発表時間:
<口頭発表>卒業論文25分(発表15分,コメント・質疑応答10分)・修士論文30分(発表20分,コメント・質疑応答10分)
<ポスター・デモ発表>卒業論文・修士論文とも掲示・質疑(コアタイム45分:15分×3セット)
使用言語:日本語または英語
予稿集:発表者の方には,2016年1月29日(金)までに,予稿集原稿(A4用紙2ページ以内)をご提出いただきますのであらかじめご承知おき下さい。発表者の方にはテンプレートをお送りします。
発表申込方法:第19回卒修論セミナーホームページ【申込フォーム】より,必要事項(発表言語での論文タイトル・キーワード(3~5語)・日本語200字程度, 英語400 words程度の発表要旨を含む)を入力・送信してください。
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「語彙学習方略研究の動向と展望」
水本 篤 先生(関西大学)
14:40-16:00 「接辞を用いた語彙指導の理論と実践」
森田 光宏 先生(広島大学)
16:00-16:20 フロアとのQ & A セッション
16:20-16:30 閉会のことば
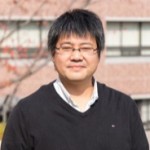 【プロフィール】水本篤(博士・外国語教育学)
【プロフィール】水本篤(博士・外国語教育学)
関西大学外国語外国語学部・外国語教育学研究科准教授
専門は語彙学習方略,言語テスティング,コーパスの教育利用。
主な著作は『外国語教育研究ハンドブック』(2012, 松柏社, 共編著),『Exploring the art of vocabulary learning strategies: A closer look at Japanese EFL university students』(2010, 金星堂)。
これまでに,学習方略,自己調整学習,Data-driven learning(DDL),量的研究手法に関する論文が,Applied Linguistics, ReCALL, Language Teaching Research, Reading in a Foreign Language, RELC Journal などのジャーナルに掲載されている。
2014年,全国英語教育学会(JASELE)学術奨励賞受賞。
website: http://mizumot.com/
学習方略(learning strategies)は外国語教育研究では1975年ごろに研究が始まり,過去40年にわたって研究が進められてきました。ともすれば,指導者側のみの観点や,認知的なメカニズムに焦点を当てることが多い外国語教育研究の中で,学習方略は学習者の視座に立った,非常に実践に近い研究分野であるといえます。
方略の使用は,学習スタイル,動機づけなどの個人差要因だけではなく,学習環境やタスクの種類などの外的な要因にも影響を受けることが知られているため,本講演では,そのような要因も考慮に入れ,これまでに何度か変遷を遂げてきた方略の定義の説明をはじめに行います。次に,語彙学習方略の種類や分類,そして語彙学習方略指導について,これまでの研究で明らかになっていることの紹介を行い,今回のセミナーのテーマである「語彙学習方略:理論と実践」に合った形で,語彙学習方略研究の動向と展望をお話ししたいと思います。

【プロフィール】森田光宏(博士・学術)
広島大学外国語教育研究センター准教授
専門は第二言語習得。特に第二言語の心的辞書に興味があり,単語認知,派生語処理,定形表現の処理を中心に研究を行っている。また,研究の知見を英語教育に活かすべく,語彙習得理論や語彙指導の研究も行っている。
平成27年度全国英語教育学会・小学校英語教育学会第1回英語教育セミナー「英語の語彙指導:その理論と教室内での実践方法」において講師を務める。
語彙学習方略は多岐にわたり,その一つ一つが学習者の語彙習得の大きな助けになります。しかしながら,接辞を用いた語彙方略は,その重要性を指摘されつつも,語彙指導に組み込まれることがほとんどない方略の一つです。一方で,英語を第一言語とする学習者を対象とする研究では,形態論的気づき(Morphological Awareness)の伸長が言語の理解や読解に重要な役割を担っていることが明らかになり,その気づきの伸長を促す指導が行われてきています。
本講演では,まず,第一言語及び第二言語としての英語学習者を対象とした接辞に関する研究を概観し,これまでに明らかになっていることをまとめます。次に,接辞を用いた語彙方略の伸長を目指した実践を紹介し,会場の皆さんと一緒により効果的な実践へのヒントを探りたいと思います。
下記のフォームをご利用ください(11月2日より受付開始)
第37回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「6年間を見据えた『共有化』の取組み」
増見敦 先生・軽尾弥々 先生(神戸大学附属中等教育学校)
14:40-16:00 「英語によるプロジェクト構築と発信の意義―立命館大学プロ
ジェクト発信型英語プログラムの試みから―」
木村修平 先生・近藤雪絵 先生(立命館大学)
16:00-16:20 フロアとのQ & A セッション
16:20-16:30 閉会のことば
 【プロフィール】 神戸大学附属中等教育学校教諭。神戸大学教育学部卒業後,神戸市立赤塚山高等学校(平成5年度~平成11年度),神戸市立葺合高等学校(平成12年度~平成23年度)を経て現職。神戸市立葺合高等学校では平成20年度より4年間,神戸大学附属中等教育学校では平成24年度より3年間英語科主任を務める。現在第4学年(高校1年段階)主任。
【プロフィール】 神戸大学附属中等教育学校教諭。神戸大学教育学部卒業後,神戸市立赤塚山高等学校(平成5年度~平成11年度),神戸市立葺合高等学校(平成12年度~平成23年度)を経て現職。神戸市立葺合高等学校では平成20年度より4年間,神戸大学附属中等教育学校では平成24年度より3年間英語科主任を務める。現在第4学年(高校1年段階)主任。
論文等 : 増見敦(2015)「高校生ライティングの流暢性の向上に適した指導回数・評価者の検討」『日本教科教育学会第41回全国大会論文集』,増見敦・石川慎一郎(2014)「高校生の英語力を推定する語彙テストの検討―サイズテストと速度テストの比較―」『神戸大学国際コミュニケーションセンター論集』,増見敦・石川慎一郎(2014)「高校生の英語受容語彙力・発信語彙力・ 語彙運用能力の関係」『日本教科教育学会第40回全国大会論文集』,増見敦(2014) 「中高一貫校での英語多読指導の科学―統計,言語分析による,英語力,言語力,自己効力感の変化を予測する科学的指導モデルの提案」『第26回英検研究助成研究報告書』,など。
 【プロフィール】神戸大学附属中等教育学校教諭。LaTrobe大学(オーストラリア メルボルン)応用言語学修士課程修了,専門はLOTE。帰国後,奈良県公立高校英語講師。2006年4月より大阪女学院中学・高等学校教諭。主に高校生の英語授業を担当。2012年神戸にてCELTAコース受講。2013年4月より現職。神戸大学附属中等教育学校5回生を1年生から担当,現在第3学年担当。
【プロフィール】神戸大学附属中等教育学校教諭。LaTrobe大学(オーストラリア メルボルン)応用言語学修士課程修了,専門はLOTE。帰国後,奈良県公立高校英語講師。2006年4月より大阪女学院中学・高等学校教諭。主に高校生の英語授業を担当。2012年神戸にてCELTAコース受講。2013年4月より現職。神戸大学附属中等教育学校5回生を1年生から担当,現在第3学年担当。
本校は,神戸大学の附属学校再編成計画の中で,旧附属明石中学校・住吉中学校を母体に,完全な中高一貫教育をめざす学校として設立されました。附属中学校の上に新たに後期課程(高校段階)を創設するという例は全国的にも珍しく,今年で後期課程発足後3年が経過し,3月に初の卒業生を輩出したばかりの新設校です。
一方,この3年間の変革期に多くの英語科教員が入れ替わりました。英語科スタッフ全員の前任校が全て異なるという「異文化」が共生する中,後期課程発足後の英語科を新しく「創る」という,一般の教員生活の中ではなかなか得ることのできない経験をして参りました。教師も不安,生徒も不安,保護者も不安…。そのような中,我々英語科が大切にしてきたことは,中高「連携」というよりむしろ「共有」。ゼロからの出発から,時間をかけて様々な「共有」の段階を登りつつ,ようやく「連携」,そして次の課題が見えてきました。
今回のセミナーでは,授業実践以前に大切な「英語科組織創り」の中で,昨今の英語教育を取り囲む様々な課題の中から,何を重点に取り上げて本校独自のものに加工してきたか(「共有」の内容),そして誰とどのように共有しようとしてきたか(「共有」のプロセス)についてご紹介させていただきます。また,生徒パフォーマンスの様子もご覧いただきつつ,全学年での授業実践の様子や具体的な指導法,また,プレゼンテーションやスピーキングテスト等のパフォーマンステスト後の指導例,そして本校の実践での成果と課題についてもご紹介させていただきます。
是非,本校の実践を「たたき台」に,今後の英語教育について参会者の皆様と貴重な意見交換を賜れますことを楽しみにしております。
 【講師プロフィール】木村修平(立命館大学生命科学部生命情報学科 准教授) 2003年5月、ミシガン州立大学社会科学部社会学科、卒業。2006年3月、立命館大学大学院言語教育情報研究科、修了。2010年4月、立命館大学外国語嘱託講師。2014年4月より現職。研究領域は、高等英語教育におけるICTの利活用。Twitter: @syuhei
【講師プロフィール】木村修平(立命館大学生命科学部生命情報学科 准教授) 2003年5月、ミシガン州立大学社会科学部社会学科、卒業。2006年3月、立命館大学大学院言語教育情報研究科、修了。2010年4月、立命館大学外国語嘱託講師。2014年4月より現職。研究領域は、高等英語教育におけるICTの利活用。Twitter: @syuhei
【講師プロフィール】近藤雪絵(立命館大学薬学部 講師)
2008年3月、立命館大学大学院言語教育情報研究科、修了。企業研修の講師・コーディネーターを経て、プロジェクト発信型英語の講師及び教材開発等担当。関心領域は、学習者主導を実現するミーティング/カンファレンス・スタイルのクラス運営と機械が苦手でも使える・作れる電子教材開発。
立命館大学では、2008年に開学した生命科学部・薬学部から必須英語カリキュラムに「プロジェクト発信型英語プログラム」(Project-based English Program, PEP)を導入しました。2010年に開学したスポーツ健康科学部、そして2016年度に開学予定の総合心理学部でも同プログラムが採用されています。学生自身の興味・関心に基づいてプロジェクトを起ち上げ、ICTを駆使しながら、伝えたいことをアカデミックなフォーマットに落とし込んで英語で発表するという特徴を持つPEPは、学内外の様々な立場の人々を巻き込んで一つの大きなプロジェクトに育ちつつあります。本講演では、PEPの概要をご紹介するとともに、PEPのようなプロジェクト型英語授業が様々な「連携」を創発する装置として駆動する仕組みを考えます。
下記のフォームをご利用ください(10月01日より受付開始)
第36回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
全国英語教育学会(JASELE)事務局からのお知らせ
本学会では,今年度より「JASELEニューズレター」のメール配信を正式に開始しております。各地区学会の協力を得て,大会情報や学会Webページの更新情報を配信しています。購読・退会・メールアドレスの変更は以下のページで受け付けています。
http://www.jasele.jp/jasele-newsletter/
仮登録の後でメールを受信して,指示に従っていただければ本登録が完了します。ぜひ,周りの先生方にもご登録を呼びかけていただければ幸いです。
上記の件,よろしくお願い申し上げます。
発 行:全国英語教育学会事務局広報/通信部(石井雄隆・長谷川佑介)
連絡先:news@jasele.jp
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「研究方法事始め:心理言語学的アプローチの基本のき」
門田修平 先生(関西学院大学)
14:40-16:00 「実践研究はじめの一歩:教師が自らの実践を対象に研究を進める方法」
藤田卓郎 先生(福井工業高等専門学校)
16:00-16:20 フロアとのQ & A セッション
16:20-16:30 閉会のことば
専門は、心理言語学、応用言語学(L2メンタルレキシコン、L2読解、シャドーイング・音読の効果など第二言語の処理・獲得のプロセスに関する研究)。主な編著書に、『英語リーディングの認知メカニズム』、『第二言語理解の認知メカニズム』、『SLA研究入門』(くろしお出版)、『英語のメンタルレキシコン』(松柏社)、『シャドーイングと音読の科学』、『シャドーイング・音読と英語習得の科学』、『英語上達12のポイント』(コスモピア)、『英語語彙指導ハンドブック』、『英語リーディング指導ハンドブック』、『英語音読指導ハンドブック』、『英単語運用力判定ソフトを使った語彙指導』(大修館書店)などがある。これまでも現在も、ことばの科学会(JSSS)、大学英語教育学会(JACET)リーディング研究会、外国語教育メディア学会(LET)関西支部基礎理論研究部会の3つを中心に活動。趣味は、やはり食べて、飲んで、語って、唄うこと。それと旅行。カラオケの選曲はポップスから演歌まで多種多様ですので、ぜひご一緒に。
【講演概要】最近の言語研究では、第一言語(母語)の研究に代わって、第二言語の研究が脚光を浴びていると、門田(2010)『SLA研究入門』(くろしお出版)では書きました。この傾向は、本講演でお話しする心理言語学的アプローチにより、その後ますます顕著になっています。学習者による英語(第二言語)の処理(processing)や習得(acquisition)という「窓」から、言語を眺める…。同時に、英語(第二言語)の習得という「知的いとなみ」から、人のこころの仕組みを調べる…。これらが明確に意識され、その結果、第二言語習得研究はさらに長足の進歩を遂げたのです。特に、私たち日本人がどのようにして、言語間距離の遠い英語を処理し習得していくかという研究は、実は新たな視点を得て、その意義が従来とは比べものにならないほどますます重要になっています。
講演では、この心理言語学アプローチについて、その概略を具体的にお話ししたいと考えています。
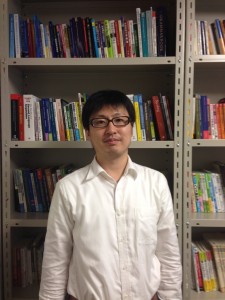 【講師プロフィール】University of Essex MA in TEFLを修了。中学校常勤講師、特別支援学校教員、高校教員を経て、現在福井工業高等専門学校で助教として勤務しています。タスクに基づいた指導法(Task-Based Language Teaching)と実践者が自らの授業を対象に行う研究(practitioner research)の方法に興味があります。
【講師プロフィール】University of Essex MA in TEFLを修了。中学校常勤講師、特別支援学校教員、高校教員を経て、現在福井工業高等専門学校で助教として勤務しています。タスクに基づいた指導法(Task-Based Language Teaching)と実践者が自らの授業を対象に行う研究(practitioner research)の方法に興味があります。
【講演概要】自分が指導しているクラスについて研究を進めたいと考えている先生方を主な対象と考え、実践を対象に研究を進める方法を、事例を交えながらお話したいと思います。特に、(1)問いの種類や立て方、(2)データの種類や収集方法、(3)データの分析方法の観点から発表をさせていただきます。「実践研究はじめの一歩」のタイトルの通り、実行可能性を重視した内容を心がけてお話したいと思います。
下記のフォームをご利用ください(09月01日より受付開始)
第35回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
2014年2月の第17回卒論・修論研究発表セミナーにおきまして,スペシャル・トークをご担当下さいました,萩原裕子先生(享年59歳)が,平成27年7月10日(金)にご逝去されました。スペシャル・トークでの言語習得の脳科学についての刺激的なご講演が,いまだ記憶に新しいところです。ここに慎んで哀悼の意を表し,ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
- 会場内に「託児コーナー」が設置されます。ご希望の方は公式サイトより申込下さい。
- 学生会員の交流の場の提供として,「第3回大学生・大学院生フォーラム」が開催されます。
2015年度関西英語教育学会(第20回)研究大会を下記の要領で開催致します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
→ プログラムのダウンロード
→ アブストラクト・スライドpdfのダウンロード
2015 (平成 27) 年
6 月 13日(土)12:10~17:45(12:00受付開始)
6 月 14日(日)10:00~16:25(9:30受付開始)
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス D号館 グローバル・コミュニケーション学部
〒650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 → アクセス
*駐車場スペースはございませんので,公共交通機関または近隣の駐車場をご利用下さい。
関西英語教育学会会員:無料
非会員 (一般):2,000 円
非会員 (学部学生・大学院生):1,000 円
*学生証をご提示下さい。提示がない場合は一般参加費となります。
*事前申込の必要はございません。当日会場にお越し下さい。
*上記参加費で2日間ご参加いただけます。会場では名札をご使用下さい。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
英語教育における小中高の接続と連携:京都教育大学附属校の取り組み
今西 竜也(京都教育大学附属小中学校)・山川 拓(京都教育大学附属桃山小学校)・黒川 愛子(京都教育大学附属桃山中学校)・磯部 達彦(京都教育大学附属口頭学校)
高校英語教科書の分析から語用論的指導の可能性を探る
水島 梨紗(札幌学院大学)
言語テストとスタンダードセッティング
清水 裕子(立命館大学)・中村 洋一(清泉女学院短期大学)
外国語能力を支える脳内メカニズム
尾島 司郎(滋賀大学)
会費:一般 3000円,学生2000円(当日,受付にてお支払い下さい)
*会場は神戸学院大学ポートアイランドキャンパス内を予定しています。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
○第1日目にご参加された方は,名札を付けて入場下さい。
○日曜日は学内食堂は開いていません。各自昼食をご持参下さいますようよろしくお願いいたします(特にランチョンセミナーご参加の皆さま)。
英語の反転授業でできること
中西 洋介(近畿大学附属高等学校)
(公募WS)創造的コミュニケーションを支える語彙・文法学習のための「めっちゃ楽しい!」アクティビティ紹介
三野宮 春子 (神戸市外国語大学)・長谷川 和代 (NPO法人GATE(小学校英語活動支援団体))・山根 貴子 (姫路市立飾磨高等学校)・大濱 さおり (南あわじ市立松帆小学校)・土井 幹生 (神戸市外国語大学学生)
言語処理の自動化を目指す音読・シャドーイング
山内 豊(東京国際大学)
英語教員のためのヴィゴツキー/バフチン理論入門
西本 有逸 (京都教育大学)
① 13:00~13:30 ② 13:35~14:05 ② 14:10~14:40
① [研究発表]わかりおメソッド:新しい英語音素指導法/秦 正哲(兵庫医療大学)
②[研究発表]ユニバーサル化した大学の英語専攻以外の学部における英語教員の役割/中原功一朗(関東学院大学)
③[研究発表]Effects of a morphological approach to raising learners’ consciousness to copular sentences/本田隆裕(神戸女子大学)
① [研究発表]小学校外国語活動における「書くことの指導」に関する一考察/山本 元子(常磐会学園大学)・和田 吉雄(大阪市立開平小学校)
② [事例報告]公立学校における幼小中一貫した英語教育の展開に向けて/高木 浩志(宝塚市立西谷中学校)
③[事例報告]高等学校における英語落語の実践報告—総合学習での試み/船越 貴美(神戸学院大学附属高等学校)・池亀 葉子・竹田 里香(特別非営利活動法人 Creative Debate for GRASS ROOTS)
②[事例報告]インターネット教材を使った留学生に対する遠隔学習/平尾 日出夫(追手門学院大学)
③ [事例報告]日本の高等英語教育における内容言語統合学習(CLIL)の導入:教育用Social Networking Website『Edmodo』を利用した反転授業形態を取り入れた実践報告/谷野 圭亮(大阪教育大学大学院生)
清水 裕子 (立命館大学,関西英語教育学会副会長)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2015年度(第20回) 研究大会 プログラム(PDF)
4月25日公開(6月10日最新版アップロード)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2015年度(第20回)研究大会 研究発表・公募ワークショップ・アブストラクト(PDF)
関西英語教育学会2015年度(第20回)研究大会 講演・セミナー・ワークショップ等アブストラクト(PDF)(5月19日現在)
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
2015年度関西英語教育学会(第20回)研究大会を下記の要領で開催致します。
今回も昨年度同様,研究大会が2日間に渡って開催され,研究発表・事例報告に加えて,公募ワークショップ・公募フォーラムの発表募集を行います。奮ってご応募下さい。多くの皆様のご発表・ご参加をお待ちしております。
日程
2015(平成 27) 年 6 月 13日(土)・14 日 (日)
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス アクセス
関西英語教育学会会員:無 料
非会員(一般):2,000 円
非会員(学部学生・大学院生):1,000 円 (※学生証を提示して下さい)
1日目:6月13日(土)
2日目:6月14日(日)
発表者は、関西英語教育学会の会員にかぎります。
※ 2015 年 4 月 20 日(月)までに,会員の方は 2015 年度の学会費を納入していることが必要です。非会員の方は、会員手続き(入会申込および会費納入)を済ませて下さい。入会手続きおよび会費納入が確認されない場合は、発表自体が取り消しとなりますのでご注意下さい。
※ 共同研究者は学会員であることが望ましいですが、必ずしも会員である必要はありません。ただし、当日の発表は学会員が行って下さい。
広く英語教育にかかわる理論的・実証的研究および授業実践に関する報告で、未発表のものに限ります。
日本語または英語
(1) 研究発表 (理論的、実証的研究の発表)
(2) 事例報告 (授業実践に関する報告)
(3) 公募ワークショップ(1人または複数の講師による英語授業実践をテーマとした企画)
(4) 公募フォーラム(コーディネータおよび数名の英語教育にかかわる理論的・実証的研究をテーマとした企画)
(1) 口頭発表(1 件につき発表 20 分、質疑応答 5 分)
(2) ポスター発表(発表コアタイム 60 分)
(3) 公募ワークショップ・公募フォーラムは1件あたり90分です。
本ページの申込フォームから、必要情報(以下の内容)を入力して送信して下さい。
2015 年 3 月 16 日(月) ~ 4 月 20 日(月) 23:59 まで
※期限厳守。期限を過ぎたものはいかなる理由があっても受け付けることができませんので,留意して下さい。
2015 年 4 月 27 日(月) までに登録されているメールアドレス宛てに、電子メールにて通知します。
※4 月28日(火) を過ぎても通知がない場合は、学会事務局(下記参照)まで電子メールにてお問い合わせ下さい。
研究発表・事例報告・公募フォーラム・公募ワークショップは,大会2日目に予定されていますが,応募数によっては,大会1日目に開催することもあります。なお,日程や時間帯の指定はご遠慮下さい。
※ 発表資格など発表応募要領をよくご確認ください。
※ 発表の内容が未発表のものであることを確認して下さい。
※ 入力内容に誤りがございますと申込手続きを進めることができませんので、ご注意ください。
※ 「申込フォーム」での送信後、登録完了のお知らせを折り返しお送りいたしますのでご確認ください。
※ ご登録いただいた個人情報は厳重に管理を行い、研究大会発表申込の手続き以外には使用いたしません。
ご自由にダウンロード・印刷・掲示ください
関西英語教育学会 2015年度(第20回) 研究大会 プログラ厶
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
平成26年度学会費納入のお願い
今年度(平成26年度)の学会費の納入がまだの方がいらっしゃるようです。該当の方は,2月末日までの納入をよろしくお願い致します。
特に,2015年8月に熊本にて開催される,第41回全国英語教育学会熊本研究大会にて,発表を予定なさっている方々は,今年度分の会費の2月末までの納入が発表資格の条件になりますので,十分にお気をつけ下さいませ。
学会費納入に際しては,以下のページをご参照下さい。
http://www.keles.jp/join/
主催:関西英語教育学会(KELES)
共催:大学英語教育学会(JACET)関西支部、外国語教育メディア学会(LET)関西支部
「第18回卒論・修論研究発表セミナー プログラム」について変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
日時:2015年2月11日(水・祝)
場所:関西国際大学 | 尼崎キャンパス | info 〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
参加費:会員、非会員とも 500円
※事前申込不要 当日,予稿集を配布 直接会場にお越しください
発表者の皆さまは必ずこちらをご覧ください
プログラム(PDF)のダウンロードはこちらからどうぞ
プログラム(PDF)2015年02月02日更新
9:00 - 受付(関西国際大学・尼崎キャンパス・5階受付にお越しください) info
9:20 – 9:30 開会行事(501中講義室)
司会: 鳴海 智之(神戸大学非常勤講師)
開会の挨拶: 村田 純一(関西英語教育学会会長・神戸市外国語大学)
9:40 – 11:55 午前の部 info
12:00 – 13:00 ポスター発表コアタイム info
12:00 – 13:20 昼食休憩
13:20 – 15:35 午後の部 info
15:40 – 17:00 スペシャル・トーク(501中講義室) info
「読解とコミュニケーションの方略研究に関わって」
講師: 平野 絹枝 先生(上越教育大学・教授)
講師紹介: 大嶋 秀樹(滋賀大学)
17:05 – 17:15 閉会行事(501中講義室)
閉会の挨拶: 大和 知史(関西英語教育学会幹事長・神戸大学)
17:30 – 19:00 レセプション
会費:一般2500円,学生1000円(当日受付にてお支払い下さい)
会場:関西国際大学・尼崎キャンパス2階食堂
どなたでもご参加いただけます。どうぞお気軽にご参加下さい!!
①9:40~10:10 ②10:15~10:45 ③10:50~11:20 ④11:25~11:55
コメンテーター:泉 惠美子(京都教育大学) ・生馬 裕子(大阪教育大学)
① B: グローバル人材育成の為の雑談授業/野坂 享資(関西大学)
② M: The Effects of Pre-Task Planning and Proficiency Level on Fluency, Accuracy, and Complexity of EFL Learners’ Oral Narrative Task Performance/意如(神戸大学)
③ M: 小学校外国語活動における教師・児童の意味生成とその過程に関する研究 /石井 健一(兵庫教育大学)
④ M: 協同学習による中学校英語授業のデザイン/江森 享子(兵庫教育大学)
コメンテーター: 里井 久輝(龍谷大学)・菅井 康祐(近畿大学)
① B: リスニング内容理解度におけるトップダウン・ボトムアップ処理の比較/片岡 寛康(京都教育大学)
② B: アンケート調査に基づいた英語子音発音教材の開発/千代島 尚紀(関西大学)
③ B: 日本人英語学習者への歌のリズムが与える効果についての一研究/西田 沙代(京都教育大学)
④ M: The Effectiveness Basic Pronunciation Exercises during Grammar Lessons/宮田 光美(神戸市外国語大学)
コメンテーター:籔内 智(京都精華大学)・谷村 緑(京都外国語大学)
① B: onlyの両義性について/野尻 祐揮(神戸市外国語大学)
② M: 日本人高校生の語彙習得における接尾辞指導の効果/東 年伸(神戸市外国語大学)
③ B: 認知言語学による句動詞の解釈 —中学校で習う句動詞に焦点を当てて—/前田 彩絵(神戸市外国語大学)
④ M: コアイメージを用いた日本人英語学習者の基本動詞学習: 学習者主導の発見学習と教員主導の明示的学習の比較研究を通して/山形 悟史(大阪教育大学)
コメンテーター: 中野 陽子(関西学院大学)・吉田 真美(京都外国語大学)
① B: リーディングの流暢性を高めるための明示的/暗示的指導の効果に関する研究/川上 順紀(京都教育大学)
② M: 日本人英語学習者の関係節文理解における統語処理プロセスの可変性 −Maze Taskによる検討−/藤田 如生(神戸大学)
③ B: 英語リーディングにおける理解と価値づけの関係性/岡林 洋平(京都教育大学)
④ M: 英語リーディング力と批判的思考能力の関係と育成/野河 幹広(京都教育大学)
コアタイム 12:00~13:00
① B: 日本人英語学習者に向けたフォーカス・オン・フォームの指導の実践と効果/ 岡﨑 千絵(京都教育大学)
② M: 母音挿入が未知語学習、語彙表象構築に与える経時的影響/大城 卓也(神戸大学)
③ M: 小学校外国語活動における教員の信念/細田 有紀(大阪教育大学)
① B: English Classes of Public Primary Schools in Japan: Problems of the New Curriculum and Suggestions for Improvements/神野 航佑(関西国際大学)
② M: スピーキング力がペア・スピーキングタスクのやり取りへ与える影響/松岡 大地(筑波大学)
③ M: 中学2年生を対象とした、文法指導の際のグラマーチャンツの効果/吉國 亘(大阪教育大学)
① B: 学校教育における英語科発音指導の改善/梅宮 直志(関西国際大学)
② M: 日本人EFL学習者の文章理解における再話の効果 −再話プロトコルの分析を通して−/劉 子君(神戸大学)
③ M: モデル音声の速度の違いから観たワーキングメモリと構音速度の個人差とシャドーイングの関係について −日本人英語学習を対象とした実証研究−/杉田 依嘉子(関西学院大学)
⑤13:20~13:55 ⑥13:55~14:25 ⑦14:30~15:00 ⑧15:05~15:25
コメンテーター: 山本 玲子(大阪国際大学)・真崎 克彦(明石市立中崎小学校)
⑤ B: 言語使用場面を想定した「タスク活動」の教材開発とその実践 —小学校外国語活動におけるコミュニケーションへの意欲を引き出すために—/梶山 茜(大阪教育大学)
⑥ B: 児童の英語によるコミュニケーション意欲を高めるための協同学習に関する実践研究/川久保 拓実(京都教育大学)
⑦ M: Introducing A CLIL Approach to Hi, friends!/樫本 洋子(大阪教育大学)
コメンテーター:横川 博一(神戸大学)・水本 篤(関西大学)
⑤ B: 英語教育教材としての漫画の一考察/栗山 敬悟(京都教育大学)
⑥ B: プレゼンテーションソフトを用いて視覚情報を語彙習得及びリーディング学習に活用する試み/大田 航平(関西大学)
⑦ M: Improving the Academic Word List for EFL Learners in Japan: Research in ICT, Acquisition, and Morphology/サルバ ミシュカ(大阪教育大学)
⑧ M: How Picture-Word Discrepancy Interferes with Picture and Word Naming in English: An Experiment for Japanese Learners of English/ドーマン多田 さおり(関西学院大学)
コメンテーター: 吉田 晴世(大阪教育大学)・今井 裕之(関西大学)
⑤ B: 高等学校用検定教科書の発問分析 —推論発問と評価発問に焦点を当てて—/森口 優太(京都外国語大学)
⑥ B: CLIL(内容言語統合型学習)実践授業における子どもの内容理解の深まり —Teacher-Child, Child-Childディスコースの分析から—/馬淵 祥子(大阪教育大学)
⑦ M: 小学校外国語活動におけるのぞましいTeacher Talkのあり方 ~学級担任の授業力向上を目指して~/矢野 智子(京都教育大学)
コメンテーター: 沖原 勝昭(京都ノートルダム女子大学)・加藤 雅之(神戸大学)
⑤ B: 異文化理解への気づきを引き出すICT(iPad)の活用 —学びの主体性・双方向性に焦点を当てて—/脇田 康平(大阪教育大学)
⑥ B: 小学校外国語活動における多文化共生の視点 —ヨルダン王妃作の絵本読み聞かせ活動を通して—/高橋 伸夫(大阪教育大学)
⑦ M: 中学生のグローバルマインドと統合的学習動機を育てる言語環境の創造 —アメリカの学校との英文手紙の交換をとおして—/伊藤 由紀子(大阪教育大学)
⑧ M: 高校英語教科書における環境問題の扱い方/柴田 茉里奈(大阪教育大学)
コメンテーター: 山西 博之(関西大学)・加賀田 哲也(大阪教育大学)
⑤ B: 英語コミュニケーションに対するライティングを通した婉曲表現の指導/笹尾 理絵(京都教育大学)
⑥ M: 動機づけを高める学習ストラテジー指導の効果:日本人EFL学習者におけるライティングでの実証研究/西本 知左(京都教育大学)
⑦ M: 中学生による協働的英語ライティング/太田 八千代(兵庫教育大学)
講師:平野 絹枝 先生 (上越教育大学・教授)
演題:読解とコミュニケーションの方略研究に関わって
英語の授業や言語の習得などにおける2つの重要な側面として、インプットとアウトプットがあります。そこで、このトークでは、主に、これらの側面における 方略の研究に焦点をあてます。具体的には、音声アウトプットのコミュニケ―ション(oral communication)方略のタイプに簡潔に言及したあと、インプットとしての読解に関する研究をさまざまな角度から概観します。特に読解における 方略、テスト時使用方略の研究の他、現在私が大学院で担当している、読解に関する授業で、特に興味深いと院生がこれまで報告してきた項目、例えば、読解力 とは何か(構成要素)、読解の影響要因、上手な読み手の特徴、テストや読解の指導、特に、現場ではなかなか指導しにくい高次レベルの能力を伸ばすための効 果的な指導法(discourse organizationとgraphic organizerの活用, main ideaの把握)などについても、実証的研究の苦労話に言及しながら述べる予定です。
● JR尼崎駅(北口)より東側遊歩道を北側へ回り込み,キューズモール東側から北側へ折れる。西へ直進し,会場校3階の入り口から,階段またはエレベータで5階受付へ。注:キューズモールは10時開店のため,朝は通りぬけできません。
学内には駐車スペースがありませんので,公共交通機関をご利用ください。
以下、発表者の皆さまに各発表形式別に簡単な注意事項を記します。(発表の形式や様子についてはこちらを参照して下さい)
発表時間:卒論 25分(15分 質疑応答 10分)、修論 30分(20分 質疑応答 10分)
パソコン:各教室にはプロジェクター(及びPC接続用のVGAケーブル)は設置されていますが,PC/Macは各自ご持参下さい。Macの場合,VGAアダプタが必要 となりますので,そちらもご持参下さい。PC/Macをお持ちでない方は,事前にセミナー担当者に問い合わせて下さい。
AV機器:CDやDVDの使用は可能です。MDやカセットは不可。
会場下見:発表会場の下見、パワーポイントスライドのテスト等は、午前の部の方は、開会行事後から第1発表の間までの時間に、午後の部の方は、昼食休憩の間に、各自で行ってください。
発表資料:予稿集・プレゼンテーションスライド(任意) 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
コアタイム:12:00〜13:00は、ポスター前に待機して下さい。
ポスター:【サイズ】 最大A0までにて作成。(一枚ものでも、A4を組み合わせても可)【貼付け】ボードに貼付け。貼付けに必要な資材は、学会事務局で準備します。【掲示時間】9:30〜15:40
発表資料:予稿集・ポスター 別途配布資料を作る場合は個別に準備して下さい。(当日大学構内でのコピーはできません)
プログラム(PDF)がダウンロードいただけます。以下の表紙をクリックして下さい(別ウィンドウ)
2015年02月02日公開
発表要旨(PDF)がダウンロードいただけます
2015年2月公開予定
第18回卒論・修論研究発表セミナー発表要旨(PDF)
プログラムや発表要旨に変更や修正が生じた場合、改訂版を公開いたしますので、定期的にご確認をお願い致します。
関西英語教育学会事務局 大和 知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
TEL: 078-803-7684 [dial-in]
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
日時:2015(平成27)年2月11日(水・祝)9:30~17:30
会場:関西国際大学 尼崎キャンパス → アクセス
〒661-0976 尼崎市潮江1丁目3番23号
内容:学部学生による卒業論文・大学院生による修士論文の研究発表(口頭発表またはポスター発表)
コメンテーター:主催・共催学会に所属する教員・研究者
関西英語教育学会では、大学英語教育学会(JACET)関西支部,外国語教育メディア学会(LET)関西支部との共催で,本年度も下記の要領で「卒論・修論研究発表セミナー」を開催致します。お忙しい時期とは存じますが、多くのご発表ならびにご参加を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
プログラムは,こちらをご覧下さい(2月2日公開)。
講師:平野 絹枝 先生(上越教育大学 教授)
演題:読解とコミュニケーションの方略研究に関わって
概要:英語の授業や言語の習得などにおける2つの重要な側面として、インプットとアウトプットがあります。そこで、このトークでは、主に、これらの側面における方略の研究に焦点をあてます。具体的には、音声アウトプットのコミュニケ―ション(oral communication)方略のタイプに簡潔に言及したあと、インプットとしての読解に関する研究をさまざまな角度から概観します。特に読解における方略、テスト時使用方略の研究の他、現在私が大学院で担当している、読解に関する授業で、特に興味深いと院生がこれまで報告してきた項目、例えば、読解力とは何か(構成要素)、読解の影響要因、上手な読み手の特徴、テストや読解の指導、特に、現場ではなかなか指導しにくい高次レベルの能力を伸ばすための効果的な指導法(discourse organizationとgraphic organizerの活用, main ideaの把握)などについても、実証的研究の苦労話に言及しながら述べる予定です。
参加費:会員、非会員とも 500円(当日、予稿集を配布)
セミナー終了後,懇親会を開催しますので,奮ってご参加下さい。
一般 2,500 円 学生・院生 1,000 円
上記の内容につきまして、変更や修正が生じた場合、本ページに掲載いたしますので、定期的に閲覧いただきますよう、お願い致します。
発表資格:学部生・院生(発表者は学会員である必要はありません)
申込期間:2014年12月13日(土)〜2015年1月19日(月)まで[厳守]
発表分野:外国語教育,外国文学,言語学および関連分野
発表形式:口頭発表またはポスター発表(参考: 発表形式の紹介)
発表時間:<口頭発表>卒業論文(発表15分,コメント・質疑応答10分)・修士論文(発表20分,コメント・質疑応答10分)<ポスター発表>卒論・修論とも 掲示・質疑(60分))
使用言語:日本語または英語
予稿集:発表者の方には,2015年1月28日(水)までに,予稿集原稿(A4用紙2ページ以内)をご提出いただきますのであらかじめご承知おき下さい。発表者の方にはテンプレートをお送りします。
発表申込方法:以下の申込フォームより,必要事項を入力して申込して下さい。フォームでの送信後,発表登録完了のお知らせを折り返しお送りしますのでご確認下さい。
第18回卒論・修論研究発表セミナー申込フォーム(2015年1月19日(月)23時59分まで)
関西英語教育学会事務局 大和知史(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば
(詳細が決定次第更新します。)
16:40-16:50 閉会のことば
「どう発音指導をすればよいのか迷っている・自信がない」という先生方の声に応えるため、研修会を企画致しました。日英語の音声比較といった基礎知識から、教室での実際的な指導法まで、発音指導の全体をコンパクトに学ぶことができる内容になっています。これにより、教室における発音指導がより積極的に行われることを期待しています。
主な内容:
【プロフィール】神戸市外国語大学大学院修了(英語学)、英国リーズ大学大学院(音声科学)留学。専門分野は英語音声学(発音指導および音響分析)。KELES理事、関西英語教育学会や外国語教育メディア学会の紀要査読委員、高校の検定教科書執筆、ジーニアス英和大辞典の発音校閲、教員研修会講師や高校への出張授業も多数行っている。外国語教育メディア学会関西支部の「英語発音教育研究部会」で14年間部会長を務める。科研では、教職課程の改善を目指している。
【プロフィール】神戸市外国語大学大学院修了(英語学)、専門は英語教育、KELES理事、LET関西支部運営委員、英語発音教育研究部会事務局・早期英語教育研究部会会員
下記のフォームをご利用ください(11月10日より受付開始)
第34回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-13:50 講演「ライティング指導のWhat, How, and Whyの研究動向」
山西 博之 先生(関西大学)
14:00-15:30 ワークショップ「<作文>からはじめるライティング」
山岡 大基 先生(広島大学附属中高)
15:40-16:10 ワークショップ解題
16:10-16:40 フロアとのQ & A セッション
16:40-16:50 閉会のことば
 山西 博之(関西大学・准教授)
山西 博之(関西大学・准教授)【プロフィール】広島大学大学院教育学研究科修了。日本学術振興会特別研究員(DC2)、愛媛大学教育・学生支援機構(英語教育センター)講師、関西外国語大学短期大学部・同外国語学部講師を経て、現在、関西大学外国語学部・同大学院外国語教育学研究科准教授。博士(教育学)。専門は第二言語ライティング研究。その中でも、ライティングのプロセス、ライティングの評価、協働的ライティング、第二言語での要約(Summary Writing)の研究に従事している。
【講演概要】 第二言語ライティング研究の第一人者である佐々木みゆき氏は、自身の研究の関心がWhat (能力論)、How (方略論)、そしてWhy (社会文化的動機づけ論) へと変化してきたと述べています。
本講演では、そのWhat, How, and Whyの枠組みを借用し、日本人英語学習者に対するライティング指導という観点から、第二言語ライティングの研究動向を概観します。同時に、指導とは切っても切れない関係にある評価の研究動向についても触れたいと思います。
 山岡 大基(広島大学附属中高)
山岡 大基(広島大学附属中高)【プロフィール】広島大学附属中・高等学校教諭。広島大学大学院教育学研究科修了。滋賀県立高校、広島大学附属福山中・高を経て現職。 著書:
卯城祐司(編著)(2014)『英語で教える英文法』(研究社)、 上山晋平(2014)『英語テストづくり&指導完全ガイドブック』(明治図書)、 大津由紀雄(編著)(2012)『学習英文法を見直したい』(研究社)(いずれも共著)など。 雑誌記事: 「導入のマネジメント-私のおすすめプラン “帯単元”でつくる導入プラン-「週刊誌型」の授業構成」 (『授業力&学級統率力』2014年10月号(明治図書)、 「授業のここにフォーカス20 まとまりのある文章を書くための 段階的練習」(『英語教育』2007年11月号(大修館)など。
【講演概要】<作文>から始めるライティング
英語科での「ライティング」と言うと、センテンスを重視する立場では「文法・構文」の練習と同化していたり、パラグラフ以上の単位を志向する立場では、「トピックとサポート」「ディスコースマーカー」のような道具を与えてのパターン練習に留まっていたり、と、要するに形式の指導に偏っていることが多いのではないでしょうか。
しかし、当たり前のことですが、言葉である以上、何かを書けば、そこには内容が伴います。そして、形式とは、伝えたい内容を最も効果的に伝えるために選ばれるものであるはずです。
たとえば、現在完了や仮定法といった形式に合わせて言いたい内容を考えるのではありません。言いたい内容を言い表すのに適しているから現在完了や仮定法を選ぶのです。あるいは、howeverを使うことが決まっていて、それに合わせて文脈を作るのではありません。言いたいことがあって、それを正確に読者に伝えるために必要だからhoweverを使うのです。
ですから、形式の指導は、ある程度までは内容と切り離して行うことも有効ですが、最終的には内容と統合させて行わなければ実効性の薄いものになると思われます。また、言語習得の観点からも、学習者のパーソナルな必要性と結びつけた方が効果的でしょう。
といっても、そう簡単に「内容と形式の統合」ができるわけではないので、いろいろと工夫する必要があります。このとき、英語科で言う「ライティング」という枠組みをいったん離れて、一般的に「文章を書く」という意味での「作文」という観点から考えると、有益な気づきがあるように思います。たとえば、国語の学習の中で読書感想文を書いた経験は多くの人が共有するものでしょうが、あの「作文」においては、どのような指導があったでしょうか。あるいは、大学入試等の小論文ではどのような指導がなされているでしょうか。
本ワークショップでは、こういった問題意識から、参加者の皆さまにも実際に作文を書いたり評価したりしていただきながら、「ライティング指導」への、より幅広いアプローチを探っていきたいと思います。
下記のフォームをご利用ください(10月01日より受付開始)
第33回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
12:50-13:00 開会のことば・主旨説明
13:00-14:20 「研究方法事始め:基本の「き」から始めてみよう」
竹内 理 先生(関西大学)
14:40-16:00 「解題リフレクティブ・プラクティス: 実践者による実践者のためのリサーチ、その理論と方法、わかりにくさの背景」
玉井 健 先生(神戸市外国語大学)
16:00-16:20 フロアとのQ & A セッション
16:20-16:30 閉会のことば
神戸市外国語大学大学院、米国モントレー大学院(フルブライト)を修了。現在、関西大学外国語学部・同大学院外国語教育学研究科・教授。博士(学校教育学)。専門分野は英語教育学(学習方略、動機づけ、ICT利用)。SYSTEMの編集委員や Language Learning などの査読委員も務める傍ら、中学校や高等学校の検定教科書執筆にも携わっている。JACET学術賞、モントレー大学院「顕著な活躍のあった同窓生」賞、LET学術賞を受賞。
【講演概要】この講演では、研究方法の基本の「き」に相当するアプローチ(量・質)について議論する。量的・質的アプローチ、それぞれの特徴や留意点について考察するほか、両者の「違い」ではなく「共通点」の方を強調する共約可能性の観点から、英語教育研究の可能性を拡げる道筋を提案していきたい。本講演が、研究の1歩目を踏み出すみなさんの後押しとなれば幸いである。なお、当日は参加型の講演スタイルをとるため、みなさんの積極的な貢献を期待したい。
 神戸市内の公立高校で12年間教鞭をとる。MA、ティーチャー・トレーナー(SIT, 米国)、学術博士(神戸大学)。現在、神戸市外国語大学国際関係学科および大学院英語教育学専攻教授。現在の関心分野はリフレクティブ・プラクティスによる教師教育、授業研究法開発。著書:『リフレクティブな英語教育をめざして』(共著)ひつじ書房、『リスニング指導法としてのシャドーイングの効果に関する研究』風間書房、『決定版英語シャドーイング』コスモピアなど。趣味、陶芸。
神戸市内の公立高校で12年間教鞭をとる。MA、ティーチャー・トレーナー(SIT, 米国)、学術博士(神戸大学)。現在、神戸市外国語大学国際関係学科および大学院英語教育学専攻教授。現在の関心分野はリフレクティブ・プラクティスによる教師教育、授業研究法開発。著書:『リフレクティブな英語教育をめざして』(共著)ひつじ書房、『リスニング指導法としてのシャドーイングの効果に関する研究』風間書房、『決定版英語シャドーイング』コスモピアなど。趣味、陶芸。
【講演概要】英語教育研究は、そもそも実践者の日々の疑問と共に生まれ、歩むものと思いますが、いつの間にか研究者がその過程や結論、あるいは日々の疑問さえも自らのものにしてまって、今はまるで研究者と実践者が別々の世界に住んでいるような観があります。学界でも現在の授業研究を科学と取るのは難しいというのは支配的な考えでしょうし、それにもまたそれなりの理由があります。
ここでいくつか質問を立ててみましょう。一つは、英語教育研究を科学たらしめているものは何なのか、二つ目は、我々が拠って立っていた科学的な方法は、日々教室で起こる現象をうまく説明し実践者や学習者の生活の向上に貢献しえるものになっているかどうか。三つめは、授業研究は誰のためにあるのかです。本発表では、こうした質問への答えを皆さんと共に求めつつ、英語教育と科学との関係について考えなおし、リフレクティブ・プラクティスを実践に迫るアプローチの一つと位置づけたうえで、それを可能にする考え方、それに伴う問題点やむずかしさを皆さんと共有したいと思います。
下記のフォームをご利用ください(09月02日より受付開始)
第32回KELESセミナー参加登録/キャンセル フォーム
事務局 神戸大学 大和知史研究室内 kelesoffice@gmail.com
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム
本学会に多大な貢献をされた宮本英男先生(享年86歳) が,平成26年7月18日(金)にご逝去されました。宮本先生は,日本英語教育学会関西支部(現在の関西英語教育学会)の支部長を長らく務められ,その後,関西英語教育学会では顧問というお立場で,また,全国英語教育学会の創立にもご尽力いただきました。ここに慎んで哀悼の意を表し,ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
関西英語教育学会 KELES 第17回卒論・修論研究発表セミナー体験記
第17回卒論・修論研究発表セミナーが,大学英語教育学会関西支部と外国語教育メディア学会関西支部の共催にて,2014年2月8日(土)に関西国際大学尼崎キャンパスにおいて開催されました。
ここでは、卒論・修論研究発表セミナーを体験した3人の方々の会の振り返り・体験記をご紹介いたします(なお、本ページの体験記は、次回ニューズレターにも掲載の予定です)。
発表者:樋口 拓弥 さん(関西大学)
タイトル:教員向け授業支援iPad/iPhoneアプリ“Yubiquitous Text”の開発
昨年度,「来年はここで発表をしよう」と思い参加した第16回卒論・修論研究発表セミナーから1年がたち,今回は発表者として参加させていただきました。発表時間帯が最後だったこともあり,そこまでに他の参加者の方の発表をたくさん聞くことができましたが,自分と同じように大学を卒業しようとしている学生の調査や分析のレベルの高さに驚かされました。
私はこれからより発展していくと考えている,タブレット端末を教育に応用するためのアプリについて発表させていただきました。自身で開発したiPad/iPhone用のアプリ“Yubiquitous Text”は,現在より多くの人からフィードバックをもらい改善を行っており,今回の発表はここまでの振り返り総括とより広いフィードバックをもらうためにはうってつけのチャンスでした。当日出会った人たちがこれから教育現場に出て,私の開発した“Yubiquitous Text”なども使いながらより良い教育環境が築かれていけばと思います。
最後になりましたが,当日コメント・フィードバックをいただいた先生方・学生の皆様,また“Yubiquitous Text”をダウンロードいただいた皆様,ありがとうございました。
参考)“Yubiquitous Text”の公式ウェブサイト https://sites.google.com/site/yubiquitoustextja/home
発表者:金澤 佑 さん(関西学院大学大学院)
タイトル:Do Listening and Oral Reading of Visually Presented English Words Affect Incidental Lexical Recognition?: An Empirical Study with Japanese EFL Learners
この度,修士論文の内容を発表する機会を頂きました。本セミナーの特徴を私なりに単語で表すなら,一つ目は「encouragement」です。大勢の方々が雪の中朝早くから会場に足を運んでおられ,私の拙い英語での発表を真剣に聞き,貴重なコメントを多数くださいました。会場を漂う凛としつつもサポーティブな雰囲気は今思い出しても居心地よく,関心をもって真摯に聞き,質問し,議論してくださった皆様の眼差しは,今なお脳裏に残っています。コメンテータを務めてくださった鬼田崇作先生をはじめ,参加してくださった皆様に,心より感謝申し上げます。
二つ目は,「variety」です。多岐にわたる発表を聞いて新しい分野への興味関心のきっかけができただけでなく,多様な参加者との交流を通じて研究・教育実践双方についての新しい見識が得られました。
このKELESという素晴らしい学問の場に巡り合えたことを嬉しく思います。ここで得た知見や励ましを胸に,引き続き博士課程で研究を続ける所存です。
発表者:南 侑樹 さん(京都教育大学大学院)
タイトル:コロケーションの学習可能性 −意味の透明さと関与負荷を考慮して−
正直な話,自分の修士論文をポスターにするのは紙幅の都合上,大変に苦慮するところがありました。しかしながら,この作業は自分が本当に伝えたいことを洗練させるために極めて有意義なことでもありました。
ポスター発表は卒業論文の際も行いました。2回の経験を通して感じたことですが,ポスター発表は随時聞き手の方々と対話を交わしながら発表を進められるというところが非常に魅力的です。結果,密な議論が可能になります。発表時間は1時間でしたが,あっという間に終わってしまう程に充実した時間で,そのやり取りの中で今後の研究につながる気づきも数多くありました。ご助言いただいた方々にこの場を借りて御礼を申し上げます。
また,ポスター発表は口頭発表と比べると和やかなムードで進めることができ,リラックスした状態で自分の研究の要旨をお話することができました。これから執筆される学部生,院生の方々には是非ポスター発表という選択肢も検討していただきたいと思います。
2014年度関西英語教育学会(第19回)研究大会が,6月7日(土),8日(日)に関西学院大学上ヶ原キャンパス国際学部にて開催されます。
プログラムをこちらに公開しておりますので,ご確認下さい。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
2014年度関西英語教育学会(第19回)研究大会を下記の要領で開催致します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
→ プログラムのダウンロード
→ アブストラクト・スライドpdfのダウンロード
2014 (平成 26) 年
6 月 7日(土)12:30~16:35(12:00受付開始)
6 月 8日(日) 10:00~15:30(9:30受付開始)
関西学院大学・上ヶ原キャンパス・国際学部
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 → アクセス
*駐車場スペースはございませんので,公共交通機関または近隣の駐車場をご利用下さい。
関西英語教育学会会員:無料
非会員 (一般):2,000 円
非会員 (学部学生・大学院生):1,000 円
*学生証をご提示下さい。提示がない場合は一般参加費となります。
*事前申込の必要はございません。当日会場にお越し下さい。
*上記参加費で2日間ご参加いただけます。会場では名札をご使用下さい。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
スローラーナーの英語指導をどうするか?
泉 恵美子 先生(京都教育大学)・加賀田 哲也 先生(大阪教育大学)・松下 信之 先生(大阪府立高津高等学校)
文法から異文化間コミュニケーションまで—基礎理論としての認知言語学概説—
田村 幸誠 先生(大阪大学)
協働的なライティング活動をどう展開するか
山西 博之 先生 (関西大学)
会費:一般 3,500円, 学生3,000円 (当日,受付にてお支払い下さい)。*会場は阪急電鉄西宮北口駅付近のお店を予定しています。
○おいでになられましたら,「参加票」に必要事項をご記入の上,受付にお越し下さい。
○第1日目にご参加された方は,名札を付けて入場下さい。
① 10:00~10:30 ② 10:35~11:05 ② 11:10~11:40
① [研究発表]わかりおモデル:英語音声指導の新しいアプローチ/秦 正哲(兵庫医療大学)
②[研究発表]英語絵本を導入した初等英語教育教員養成プログラム開発に
ついての研究/脇本 聡美(神戸常盤大学・兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生)
③[研究発表]英文法指導に関する教員意識-中学校教員と高等学校教員の比較-/神山 豊彦(五條西中学校)
① [事例報告]英語自主学習施設の効果/山岡 賢三(樟蔭学園英語教育センター)
② [研究発表]2014年における「授業で使える英語の歌」/伊庭 日出樹(兵庫県立淡路三原高等学校)
③[事例報告]中学校英語教育の現状と課題について-管理職の視点からの提言-/高木 浩志(宝塚市立宝塚中学校)
① [事例報告]生徒の困り感に寄り添う英語指導の手立て~英語とICTと支援教育~/森田 琢也(大阪府立とりかい高等支援学校)
② [研究発表]英文法指導におけるリメディアルの試み:CLTと伝統的教授法の折衷/井上 聡(環太平洋大学)
③ [研究発表]中学1年生を対象としたイメージ利用の基本動詞学習-カードゲーム学習と明示的指導の比較研究から見えたこと-/山形 悟史(大阪教育大学大学院)・吉田 晴世(大阪教育大学)
第1室【201】
第二言語ライティング研究—目の前の現象をどう捉えて,未来に生かすか—
佐々木 みゆき 先生(名古屋市立大学)
第2室【202】
1年間の留学が学生の英語力と情意面に与える影響—メタ言語知識の役割—
飯田 毅 先生 (同志社女子大学)
清水 裕子 (立命館大学,関西英語教育学会副会長)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2014年度(第19回) 研究大会 プログラム(PDF)
4月29日公開(5月1日修正版公開)(5月31日修正版公開)
ご自由にダウンロード・印刷・掲示・配布することができます
関西英語教育学会 2014年度(第19回)研究大会 発表アブストラクト(PDF)
(5月23日 研究発表・事例報告アブストラクト公開)
※本ページに掲載の内容は変更される可能性があります。定期的に最新情報のご確認をお願い申し上げます。
6月8日
関西英語教育学会事務局 横川 博一(神戸大学)
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
E-mail: yokokawa@kobe-u.ac.jp
※お手数ですが@マークを半角文字に置き換えてください。
または次のお問い合わせフォームをご利用ください
事務局お問い合わせフォーム